| |
|
|
| |
農経しんぽう |
|
| |
令和7年2月24日発行 第3541号 |
|
| |
|
|
| |
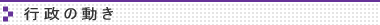 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
水田農業を高収益化/北陸農政局がオンラインセミナー |
|
| |
|
|
| |
北陸農政局は19日、北陸高収益サロン「スマート農業技術の導入促進」をオンラインで開催した。
同サロンは、水田農業の高収益化の推進を目的に、生産者や地域の関係者が集うイベント。今回はスマート農業技術がテーマということで、(株)ISEKI Japan関西中部カンパニー、(株)北陸近畿クボタおよびクボタアグリサービス(株)、(株)DONKEY、ヤンマーアグリジャパン(株)中部近畿支社、REACT(株)の農機メーカー5社が登壇し、農業用ドローン、ラジコン草刈機、自動操舵システムなどのプレゼンテーションを行った。
ISEKI Japan関西中部カンパニーは、直進アシストトラクタBFシリーズと、CHCNAV社製の後付け自動操舵システムを紹介。両者を比較しながら、後付け自動操舵システムは直進に加えて条合わせができることや、製品の低価格化が進み100万円程度で入手可能なことなどを説明した。
北陸近畿クボタおよびクボタアグリサービスは、農業用ドローンやラジコン草刈機を紹介。このうち農業用ドローンについては、KSASとの連携により、作業日誌の自動作成や作業軌跡の再生、進捗の確認などが容易にでき、利用の幅が広がることを強調した。
ヤンマーアグリジャパン中部近畿支社は、ラジコン草刈機YW500RCについて、45度までの傾斜地に対応できることや、ボンネットとガードパイプの一体型でメンテナンスがしやすいことなどを特徴としてあげ、労力軽減につながったとする利用者の声も紹介した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
6年度鳥獣対策活動を表彰/農林水産省 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は14日、都内霞が関の同省7階講堂にて、令和6年度鳥獣対策優良活動表彰式を開催した。
これは、鳥獣被害防止や捕獲した鳥獣の食肉(ジビエ)の利活用等に取り組み、地域に貢献している個人や団体を表彰するもの。開会挨拶した滝波宏文農林水産副大臣は、野生鳥獣による農作物被害額は令和5年度に164億円となり、平成22年度の239億円のピークから減っているが、鹿やクマの被害増加により前年に比べてやや増加したと指摘。鳥獣被害は営農意欲の減退や耕作放棄・離農の増加など農山漁村に甚大な被害を与えており、農林水産地域を美しく活力あるものとして次世代に継承していくためにも、各地で必要に応じた鳥獣対策を地域一体となって進めていくことが重要と説明。受賞者は様々な工夫を重ねながら各地域で先進的に被害対策やジビエ活用に取り組まれているとし、その尽力に敬意を示すとともに、そうした優れた取り組みを模範事例として各地で効果的な対策やジビエの取り組みが広がることを願うなどと語った。
続いて表彰が行われた。今年度は農林水産大臣賞に下関市豊北町大字田耕「朝生地区」(被害防止部門、山口)及び(株)ART CUBE(捕獲鳥獣利活用部門、京都)の2件が選ばれ、滝波副大臣から表彰状が授与された。また、農村振興局長賞には郡山市田村町田母神集落(被害防止部門、福島)、福井市神当部区(同、福井)、坂本自治会「サル追出し隊」(同、三重)、本川哲代氏(捕獲鳥獣利活用部門、北海道)、(株)メルセン(捕獲鳥獣利活用部門、長野)、ジビエ工房やまと(同、熊本)―の6件が選出され、前島明成農村振興局長から授与された。
表彰式の後、同会場において第12回全国鳥獣被害対策サミットが開催された((株)プランドゥ・ジャパン主催、Web併催)。鳥獣対策に携わる関係者の情報共有の場として毎年行われているもので、今回は「獣害対策の『転換点』〜成功までの過程から学ぶ〜」をテーマに開催した。サミットは2部制になっており、第1部は6年度鳥獣対策優良活動表彰の受賞者が取り組みを報告し、午後の第2部は全国の鳥獣被害対策の事例講演・パネルディスカッションを実施した。
また、同会場の近傍会議室において、鳥獣被害対策や利活用に係る資機材やカタログの展示、ポスターセッションも行われた。出展の一部をみると、(株)アエロジャパンは効率的な駆除を行うハンティングドローンの実機を展示。(株)ほくつうは特定害獣の出没を検出する高精度AI・通報システム「Bアラート」を紹介。(株)メルセンはニホンジカ革を用いた財布などの商品やペットフード(革ガム)などをアピールしていた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
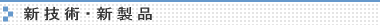 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
新型の光選別機を投入/サタケ |
|
| |
|
|
| |
(株)サタケ(松本和久社長・広島県東広島市西条西本町2の30)は3月1日、多用途シュート式光選別機「SLASHβPLUS(スラッシュベータプラス)」を発売する。「ピカ選αPLUS」の後継機として、従来機の自動検量線作成システムや、清掃・メンテナンスが工具レスで行える構造はそのままに、選別性能とユーザビリティの更なる向上を図っている。
サタケは2014年、米以外の雑穀や種子、プラスチックなど多様な原料に対応した光選別機「ピカ選α(アルファ)」を発売。翌年には形状選別機能を搭載した「ピカ選αPLUS(アルファプラス)」を開発し、より幅広い原料に対応することで多くのユーザーが利用している。
このたび開発した光選別機「SLASHβPLUS」は「ピカ選αPLUS」の後継機として、従来機の自動検量線作成システムや、清掃・メンテナンスが工具レスで行える構造はそのままに、選別性能とユーザビリティの更なる向上を図った。
超高速応答のピエゾバルブを搭載することで、不良品をエアで除去する際に発生していた巻き添えを従来機から10%低減。また、1パターンのみであったエアの噴射を2パターン設定できるようになった。これにより、今までタイミングが合いにくかった軽量の不良品など、粒速の異なるものにも対応できるようになり、選別精度と歩留まりが向上する。
光源はCCFL(冷陰極蛍光灯)からLEDに変更することにより、運転開始時の暖機時間を30分から5分へと大幅に短縮。また、光源の寿命も約1・5倍となった。外部入出力を選択式とし、ニーズに合わせて前後の工程の機械と連携させることができるようになった。
販売価格はオープン価格。農産物加工・リサイクル業者など幅広い業界へ向け、初年度30台の販売を見込む。
【特徴】
(1)ピエゾバルブの採用=従来比約1・7倍のバルブ開閉速度により選別時の巻き添えを10%低減▽バルブ開閉部に特殊素材を採用し、約3倍の長寿命化を実現▽エア消費量及び消費電力を低減(2)光学部に4色LEDを採用=運転開始時の暖機運転を30分から5分に短縮▽光源の寿命を従来機の約1・5倍に延長▽光源に3色(R・G・B)および白色LEDを採用し、選別環境や原料に応じて最適なパターンで照射することが可能(3)噴射パターンを2パターン設定可能=異物の中でも落下速度が遅く選別が難しかった軽量の異物に合わせて、2パターン目の噴射時間を設定することで選別精度を向上(4)外部入出力信号を追加=従来機ではアラーム信号のみが出力できたが、ワイパー信号、運転信号の出力を追加。これにより前後の工程の機械と連携し、エラー発生時以外でも運転制御が可能。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
広く対応する掘取機/広洋エンジニアリング |
|
| |
|
|
| |
(株)広洋エンジニアリング(久一旬弥社長・埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷78)の「B型振動掘取機」は、ゲージ輪、掘取刃の組み合わせで様々な作物に適応できる万能式の掘取機。ゲージ輪2つのU字タイプは中心掘りで型式の頭文字がBU、同1つのOタイプは側状掘りで同BOになる。BU型の適応トラクタは〜50PS(カテゴリー1)、BO型も同様だ。
BU型の型式別対象作物は、▽BU―70A=ニンジン、サトイモ▽同90A=ニンジン、サトイモ、ホウレンソウ▽同110A=ニンジン、ラッカセイ、タマネギ、ニンニク、ホウレンソウ▽同120A=同▽同130A=ニンジン、タマネギ、ニンニク、ホウレンソウ▽同140A=同。
BO型の型式別対象作物は、▽BO―200B=ダイコン(1条掘)、短根ゴボウ(ベタ)▽同403A=ネギ、短根ゴボウ(畦盛)、根ミツバ▽同404A=ネギ、エダマメ、ウコン、京イモ▽同600B=ニンジン、ホウレンソウ(硬質土壌)、グラジオラス、バラ▽同90=ちぢみ(寒締め)ホウレンソウ用根切刃(掘取刃としての使用は不可)。
さらにBU型の場合、オプションのフォーク(Y型、S型、D型、A型)を組み合わせることで、バレイショ、ヤーコン、カンショ、サトイモ(重粘土質)、タラノ芽、シャクヤク、ウド、アスパラ、ミョウガにも対応。同社は、さらに各地域の特産作物にも積極的に応える方針だ。
このほか、好条件の圃場に適した非振動式・牽引式の「K型掘取機」(UタイプとOタイプ)があり、共通フレームに各掘取刃を組み合わせて装着できる。掘取刃と収納装置はB型と共通になる。
他方、ロータリ装着式サブソイラー「ニューロータリソイラーNRシリーズ」は、ロータリ耕とサブソイラー耕を同時進行させるW耕法で作業時間を大幅に短縮できる。表層は細かく、下層は粗くの理想的な土壌構造を低馬力トラクタにより1行程で仕上げることができ、作物の生育に最適な環境を作り出す。適応トラクタについては、12PS以上には同機のNR―1A、同18PS以上には同―2A、同25PS以上には同―3Aがそれぞれ対応する。
(1)シャーボルトは、新型はせん断力によるシャーボルト1本としたため、交換が容易になった(2)破砕刃(ナイフ)はレーザー加工による曲線型とし、これにより取り付けの全長が短くなった(3)チゼル形状は、平面1枚板をナイフに溶接していた形から、新型は取り付け交換可能とし、心土の破砕効果が向上するとともに、チゼルのみの交換で耐久性も向上している―などの特徴がある。耕深は標準40センチで、35〜45センチの範囲で3段階に調節できる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
加工用の葉ねぎ収穫機で労働時間74%削減/ニシザワ |
|
| |
|
|
| |
野菜の洗浄機や選別機などを製造開発している(株)ニシザワ(西澤准一社長・香川県仲多度郡多度津町北鴨3の1の50)が香川県農業試験場と共同開発した加工・業務用葉ねぎ収穫機「NPSH―4」は、3〜4条の多条植え葉ねぎ栽培に対応可能だとして注目を集めている。
同製品の作業は2人組で行い、1人はコンテナやフレコンバックへの整列収納を補助し、満量になれば交換する流れだ。実証実験では作業時間は4・2時間/10アールと、手作業の労働時間を74%削減した。また精度も高く、刈取り収量が6・9キロ/畝メートル以上で倒伏がない条件下では、刈取りミス、搬送ミスともに1%未満で、損傷も3%未満だった。機体は電動・ハイブリッド仕様で、携帯型の発電機を搭載し、バッテリーの電力低下時は補充電しながら作業を行う。
同社によれば、同製品の性能を十分に発揮できる4・9ヘクタール以上の圃場を持つ葉ねぎ生産法人などを対象に実演を行っており、依頼に応えていくという。
〈製品仕様〉
▽寸法=全長1840(格納時1550)×全幅1970×全高1320ミリ×最低地上高330ミリ▽重量=440キロ▽適応条数・条間=(1)3条・360ミリ(2)4条・240ミリ▽適応畝高・畝裾幅=100〜250ミリ・134ミリ以下
▽製品問い合わせ=同社TEL0877・33・2438
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
芝用の新規殺菌剤の提供開始/BASFジャパン |
|
| |
|
|
| |
BASFジャパン(株)(石田博基社長・東京都中央区日本橋室町3の4の4)は14日より、最新の有効成分Pavecto(パベクト)を含有する殺菌剤「ピュアスターフロアブル」をゴルフ場芝生向け製品として提供を開始した。また、新規殺菌剤「マックスティーマフロアブル」と「エボリティフロアブル」の上市を4月上旬に予定している。これらの3つの製品は、近年の異常気象による高温化で厳しさが増している芝の病害防除をサポートする。
「ピュアスターフロアブル」は、同社と住友化学が共同で開発した新規有効成分Pavecto(パべクト/化合物名:メチルテトラプロール)を使用した殺菌剤。パべクトは主要な作物病害に効果を示し、西洋芝のベントグラスにおいては、夏に発生する炭疽病に対する優れた予防・治療効果を発揮する。近年の異常高温で増加傾向にある炭疽病に対する有効な防除手段となる。2024年の高温期に行った試験では薬害が確認されておらず、ベントグラスに対する高い安全性が特徴となっている。
DMI有効成分Revysol(レビゾール/化合物名:メフェントリフルコナゾール)は、同社が開発した世界初のイソプロパノール・アゾールの殺菌有効成分。DMI系統でありながら、DMI低感受性菌への効果が期待される。
マックスティーマフロアブルは、ベントグラスの炭疽病、ダラースポット病、葉腐病(ブラウンパッチ)、フェアリーリング病、バミューダグラスのカーブラリア葉枯病など、幅広い病害スペクトラムを有している。植物に対する安全性も高く、暑い夏の過酷な条件下での使用に適している。
エボリティフロアブルは、ともに同社が開発した有効成分である、DMI殺菌剤であるレビゾールと、高い実績を持つXemiumu(ゼミウム/化合物名:フルキサピロキサド)の混合剤で、より安定した効果が期待でき、抵抗性管理に有効。レビゾールは果樹向け殺菌剤「ベランティーフロアブル」、ゼミウムは果樹用殺菌剤「アクサ―フロアブル」と畑作用殺菌剤「イントレックスフロアブル」にも使用されており、農作物の病害防除で効果・実績のある殺菌剤を芝生にも展開していく。
国内のゴルフ場で主に使用されているベントグラスは寒冷地型の芝種であるため、夏場の猛暑によるダメージを受けやすく、コースの芝が枯れる被害が多発している。夏に発生する病害のコントロールは芝生管理者にとって重要な課題であり、同社は新たな殺菌剤を提供することで、ゴルフ場のグリーンキーパーや芝生管理者の負担を軽減し、芝が厳しい夏を乗り越えられるようサポートしていく。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
耕畜連携を後押し/田中産業 |
|
| |
|
|
| |
田中産業(株)(田中達也社長・大阪府豊中市浜1の26の21)は、各地で開かれている春の農機展に出展、同社の各商品PRに力を入れている。その中で、「スタンドバッグシリーズ」については、飼料用米、大豆などの収穫作業での活用をアピール、メッシュ素材によるムレの防止、自立型のためホルダーが不要などの利点を掲げている。
同シリーズには、▽プロスター=容量1300リットル、1700リットル、1900リットル(いずれもRC用)▽スター=800リットル、1300リットル(通常用とRC用)、1700リットル(同)▽角スター=1操作式のRC用1300リットル、同1700リットル、2操作式のRC用1300リットル、同1700リットル▽角プロ=2操作式のRC用1300リットル、同1700リットルを揃え、作業規模に合わせて選択できるようにしている。
このほか、飼料用米や籾米の流通保管には3段積みが可能な「コンテナバッグ」(規格=φ1150×高1300ミリ、最大充填量1080キロ)の受注にも対応。同バッグは食品衛生容器法のJIS規格適合品になる。
耕畜連携が喧伝されている中、飼料関連の流通促進は地域課題でもあり、このところは子実用トウモロコシの生産拡大に伴い、バッグ需要も増加傾向にあるという。
スタンドバッグの特徴は、(1)自立型でホルダーが不要(保管時は折りたたんで収納でき、場所をとらない)(2)投入口が全開でき投入がラク。排出はボタンを押して排出ハイランドロック(黄色いひも)を引くだけと簡単・スピーディー。バッグ下に入らずにできるため安全に作業できる(3)収納はクルッとひねるだけでコンパクトに折りたたみ、女性でも楽に運ぶことができる―と、取り扱いやすさには定評がある。
別売りの「モミクーラー」を使えば、一時貯留時もムレることなく良質な状態を維持、籾ムレ防止に役立つ。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
V溝直播機用補助ホッパー/鋤柄農機が発売 |
|
| |
|
|
| |
鋤柄農機(株)(鋤柄忠良社長・愛知県岡崎市矢作町字西林寺38)の不耕起V溝直播機は、高速作業で大面積の播種が可能なため、担い手や大規模農家から好評を得ている。このたび不耕起V溝直播機に装着する補助ホッパーを新たに販売した。種籾や肥料の積載量が3倍に増加し、無補給で播種できる面積が大幅に広がったことで、効率化、省力化へのさらなる貢献が期待されている。
同機は愛知県農業総合試験場が開発した、水稲の不耕起V溝直播栽培を行うことができる。
V字型の溝を切り、種籾と肥料を同時に播くことで育苗と田植え作業を省略でき、中干しも不要となる省力稲作技術。移植栽培に比べ労働時間の30%削減や、作業期間の分散ができることから、栽培面積の規模拡大が可能となるため、担い手や大規模農家を中心に導入する人が増えている。
冬季に耕起、代掻きした後に乾田化し、春先に種籾と専用肥料を直播する。ロータリー軸に作溝輪を20センチ間隔に装着して、強制駆動でV形の播種・施肥溝を切る。中央部に設けた接地輪で播種・施肥部を駆動するため、作業速度が速くなっても播種・施肥量は変わらない。播種・施肥量の調節は横溝ロールの開度調節で行い、種子・肥料はV溝に播種ホースで案内し混合されたものを播く。覆土はチェーンの端末に付けた重錘をV溝の上を引きずってV溝内に少量の土を落とす。播き終わりの工程で条数の端数が生じた場合は、重複する条数の種子・肥料の繰り出しを止めることができる。V溝の深さが保たれている間は、鳥害を抑えることができる。
オプションの補助ホッパーは、種籾や肥料の容量を3倍に増やすことができ、ステンレス製でサビに強い。これまでより広い圃場を、無補給での播種作業が可能となる。
〈補助ホッパー仕様〉
▽容量(10条用/12条用)=種籾(102・1/123・2リットル)・肥料(170・5/204・1リットル)
▽積載重量=種籾(63・3/75・8キロ)・肥料(125・3/150キロ)
▽本体+補助ホッパーの種籾と肥料の合計積載重量=292・9/350・9キロ
▽本体+補助ホッパーの無補給播種可能面積=種籾(134・3/161アール)・肥料(99・5/119・1アール)
直播栽培は全国各地の展示会で「今話題の直播栽培」と紹介され、講習会が開催されている。どこも立ち見が出るほどの盛況で、多くの農家から高い関心が寄せられている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
薬剤散布ボート/ワイズファクトリー |
|
| |
|
|
| |
(株)ワイズファクトリー(林義浩社長・千葉県印西市山田1783の1)が供給する薬剤散布ボード「ワイズボート」は、1ヘクタール作業をおよそ10分で完了する省力化マシン。農薬散布用のラジコンヘリで培ってきた様々なノウハウを盛り込み、効率性と信頼性を兼ね備えた次世代の薬剤散布ボートになっている。また、新たに独自開発した粒剤散布装置「YFR―10」(特許申請中)をオプションとして用意し、さらに活用範囲を広げた。
ワイズボートYF―260Rは、燃料、薬剤を除く船体重量が13キロと軽量で、運搬時の負荷を軽減。軽トラックで運搬できるコンパクトな設計となっている。12リットルと余裕のある薬剤タンクを搭載しており、約2・4ヘクタールまで散布が可能。エンジンはラジコン専用のゼノアエンジンG260PUHを採用し、従来の課題であった振動の低減とトルクアップを実現した。燃料タンク容量は600cc。これで約60分稼働できる。
送信機はFutaba製スティックタイプを採用。スティックの改良でアクセルも一定走行が可能となる。また、送信機側から薬剤散布量の無段階調整が可能。万が一、電波が遮断された場合でもフェールセーフが作動してエンジンがアイドル状態となり、薬剤も自動でカットされる。さらに送信機同様に高い性能を誇るFutaba製ジャイロを採用。強風時でもジャイロを搭載していることで高い安定性を実現。ジャイロ効果により、高い直進性も確保している。
粒剤散布装置のYFR―10は、10メートルの散布幅で散布でき、10キロの粒剤が搭載可能なタンクを装備。1キロ粒剤から豆つぶ剤まで、様々な粒剤をそのまま散布できる。
YF―260Rの主な仕様は次の通り。
▽機体寸法=全長1300×全幅800×全高560ミリ▽エンジン排気量=25・4立方センチ▽エンジン最高出力=1・71キロワット/1万3000rpm▽最高時速=30キロ▽電波種・到達距離=2・4ギガヘルツ/150メートル
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
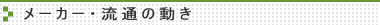 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
デジタル本部長に奥山氏/ヤンマーHD・役員人事 |
|
| |
|
|
| |
ヤンマーホールディングス(株)(山岡健人社長)は2月21日、役員人事および主要人事を発表した。内容は次の通り(敬称略)。
(2025年4月1日付)
▽非常勤取締役(取締役ブランド部長〈CBO〉)長屋明浩▽デジタル本部長(AI戦略推進部長)取締役DX担当〈CDO〉奥山博史▽マーケティング部長 山本多絵子
(2025年6月25日付)
▽取締役〈CMO〉マーケティング部長 山本多絵子
▽(退任)非常勤取締役 長屋明浩
なお、6月25日付の人事は、6月の同社定時株主総会、取締役会、監査役会において正式に決定される。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
社員決起大会を開催/新潟クボタ |
|
| |
|
|
| |
(株)新潟クボタ(吉田丈夫社長・新潟県新潟市中央区鳥屋野331)は2月14日、市内新潟ユニゾンプラザで「第63期社員大会」を開催した。約400名の社員が参加し、(株)クボタ農機国内本部の鶴田慎哉本部長が来賓を代表して挨拶した他、昨年の優秀拠点・社員に対する表彰、今期の経営方針の発表などが行われ、今年の勝利を目指して結束を固めた。
開会後、社長挨拶で登壇した吉田社長は、昨年の地震や燃料価格の高騰、米不足など、変化の大きな1年を振り返りつつ、その中で5年連続で特別優秀ディーラーを獲得できたことに感謝の意を表した。また「午前中は成績優秀者への表彰を行い、午後からは経営方針を伝えることで、社員の心を一つにする場としたい」と述べた。
続いて、来賓挨拶に立ったクボタの鶴田本部長は2024年を振り返った後、2025年のクボタ農機国内本部の方針について言及。また、新潟クボタに対し、クボタグループを牽引し、特別優秀ディーラー賞、コンバイン優秀ディーラー、占拠率優秀ディーラーを獲得したことに対し、祝意を述べた。2025年も「安全・品質・コンプライアンス」、「アフターマーケット事業」、「事業領域の拡大」を大きな3つの柱として、『スマート農業はクボタ』を合言葉に、さらなるスマート農業の浸透を進める方針を表明した。
次に、第62期(2024年)年間表彰を行い、表彰者に対して、インタビューを行うなど、和やかな雰囲気の中で会は進んだ。
SMAサポート(株)の井出理氏を講師に招き、安全運転講習が行われた後、吉田社長が63期経営方針を説明。経営計画書を参加者全員で読み合わせる形で実施した。はじめに昨年1月に改定した経営理念について改めて話し、その後、昨年の振り返りと各部の方針を示した。主な方針は次の通り。
▽第一営業本部=変化の先頭に立ち、全員参加で実施(スマート農機提案)、収益性の向上▽第二営業本部=新潟クボタらしさの追求(各領域での商品・サービスの展開)▽サービス本部=デジタル化、マネジメント▽管理本部=働きやすさと働きがいの追求
なお、同社では事業環境の変化に対応するため、今年から営業本部を第一営業本部と第二営業本部に組織変更し、農機事業を第一営業本部で管轄。第二営業本部では農業施設、車輌・特販、米穀・肥料、ファーム事業を管轄することとなった。
閉会挨拶は吉田至夫会長が務めた。昨年の猛追と今年に入ってからのスタートダッシュに謝意を表した後、「社長方針に基づき、全員が自信を持ち、少し上を向いた取り組むを行うことで善循環を生み出し、良い一年にできる」と述べ、会を結んだ。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
マジックライスが誕生30周年/サタケ |
|
| |
|
|
| |
(株)サタケは今年、マジックライス発売30周年を迎えた。
同社は1896年に日本初の動力式精米機を開発して以来、世界の三大穀物である米・麦・トウモロコシを中心に穀物加工技術の研究開発を重ね、世界約150カ国に製品や技術を提供してきた。
1990年、乾燥米飯生産設備の開発に着手。翌年にスペインの精米企業に最初の設備を納入し、1995年には、日本の米に適した乾燥米飯製造設備が完成。製造設備の販売推進と共に乾燥米飯の需要拡大を目指し、「マジックライス」を発売した。発売当初は中身を耐熱容器に移し、水を入れて電子レンジで調理するものであったが、現在はお湯または水を適量加えるだけで乾燥したお米がふっくらとしたごはんに戻るため、調理時間の短縮や簡便性が人気を博している。
また、長期保存が可能なことから、地震や台風、大雨などの自然災害時の防災食として多くの自治体や企業に採用されている。さらに、手軽に持ち運べる点が評価され、登山やキャンプなどのアウトドア食としても親しまれ、幅広く活用されている。
2022年に発売を開始した「ななこめっつ」シリーズは、従来のマジックライスより保存期間を2年延長し、7年間とした。さらに、お湯での調理時間を15分から7分へ短縮させることに成功。このほかにも、ユニバーサルデザインフードの適合商品であるおかゆシリーズや、アレルギー物質に配慮した商品ラインアップの実現により、幼児から高齢者まで幅広い年齢層に利用されている。また、2023年には「ハラール認証」を取得したことで、宗教や食文化の多様性に配慮した商品展開を進めている。
サタケ食品事業本部・本部長の大塚隆弘氏は「日頃よりご愛顧いただき、心より感謝申し上げます。おかげさまでマジックライス発売30周年を迎えることができました。これからも安全・安心・美味をモットーに新商品販売に向けて取り組んでいきたいと考えています」とコメントしている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
フードテックジャパンで光選別機を実演/サタケ |
|
| |
|
|
| |
(株)サタケは25日から3日間、インテックス大阪で開催される「第4回フードテックジャパン大阪(食品工場の自動化・DX展)」に出展する。
同展は、食品工場が抱える人手不足や労働環境改善などの問題解決を目的とした「自動化・DX・省人化」に特化した展示会。
サタケは、良品・不良品を選別する光選別機を各種出展する。シュート式光選別機では「ピカ選αPLUS」の後継機として選別性能とユーザビリティの向上を実現した「SLASHβPLUS(スラッシュベータプラス)」や、近赤外線を活用して良品と類似色・異材質の異物選別を可能にした「SLASH(スラッシュ)」の実演を行う。
ベルト式光選別機では可視光・近赤外線に加えX線カメラを搭載し、AIとの組み合わせにより内部不良の選別を可能にした「BELTUZA SPECTRA(ベルトゥーザ・スペクトラ)」の実演とパネル展示を実施する。3機種ともサタケ独自の自動検量線作成システム「サタケ・スマート・センシティビティ」を搭載しており、省人力化に貢献している。
サタケの展示は2号館の3―14ブース。開催時間は午前10時〜午後5時まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
売上高は1684億円/井関農機・2024年12月期連結決算 |
|
| |
|
|
| |
井関農機(株)(冨安司郎社長)は14日、オンラインで会見し、2024年12月期連結業績(日本基準)を発表するとともに、一昨年11月14日付で発足した「プロジェクトZ」の施策の進捗状況、また昨年2月に公表した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」の現状分析・評価、取り組み状況をアップデートした。それによると、2024年12月期の売上高は1684億2500万円(前期比99・1%)の微減。損益面は、営業利益は19億2000万円(同85・2%)、経常利益15億7700万円(同75・4%)、税金等調整前当期純損失は15億3100万円(前期は19億円の黒字)、親会社株主に帰属する当期純損失は30億2200万円(同2900万円の黒字)となった。次期の売上高は1705億円を見込み、営業利益はプロジェクトZ施策の効果発現になどより当期比6億7900万円増加の26億円を見込んでいる。なお、役員異動では深見雅之取締役が2025年3月27日付で退任、エグゼクティブ・シニア・アドバイザーに就任する予定。
会見には、冨安社長が出席した。
2024年12月期業績について冨安社長は、前期比減収減益ながら、「売上げ・利益ともほぼ昨年7月18日に公表した予想通りに着地した」と述べた。国内外価格改定効果については、「2024年は18億円の増益効果があり、原材料等仕入れ価格の高騰を上回った」とした。また、2025年12月期業績予想は「前期比増収・増益」とし、売上高は、欧州は高水準維持、北米・アジア増収、国内は成長分野への経営資源集中・販売強化で増収とする一方、利益面では増収とプロジェクトZ効果一部発現で営業増益も、一時費用があり増益幅は「限定的」とした。冨安社長は「減収減益、最終損失という厳しい決算となった。業績修正で想定していた通りだったが、プロジェクトZを完遂することで、きちっとした決算ができるように経営陣一同、プロジェクトZ完遂に向けて歩んでいきたい」と述べた。
決算概要は次の通り。 当期(2024年1月1日〜2024年12月31日)の売上高は、前期比14億9000万円減少し、1684億2500万円(前期比0・9%減)となった。国内売上高は前期比2900万円減少の1130億3100万円(同0・0%減)となった。農機製品は第1四半期は需要低迷を受け減少したが、年央以降の米価上昇による需要回復を捉え一部カバーし、通期では微減となった。一方、収支構造改革の柱である補修用部品や修理整備等のメンテナンス収入は伸長し、国内売上全体では前年並みとなった。
海外売上高は前期比14億6000万円減少の553億9400万円(同2・6%減)となった。北米はコンパクトトラクタ市場が弱含みに推移、アジアは韓国での在庫調整実施とアセアンで需要軟調となった。一方、欧州は景観整備向け製品と仕入れ商品(電動商品)の売上げが堅調に推移した。
営業利益は前期比3億3300万円減少の19億2000万円(同14・8%減)となった。国内外価格改定効果等により売上総利益は増加したが、為替換算影響もあり販管費が増加した。
経常利益は前期比5億1500万円減少の15億7700万円(同24・6%減少)となった。主に為替差益の減少と持分法による投資損失の拡大によるもの。
税金等調整前当期純損失は15億3100万円で、これは主にプロジェクトZの構造改革に伴う減損損失及び事業構造改革費用の計上によるもの。親会社株主に帰属する当期損失は30億2200万円(前期は2900万円の黒字)となった。
商品別の売上げ状況は次の通り。
〔国内〕
整地用機械(トラクタ、耕うん機など)は212億6400万円(同3・7%減)、栽培用機械(田植機、野菜移植機)は65億7400万円(同9・1%減)、収穫調製用機械(コンバインなど)は163億4600万円(同3・8%増)、作業機・補修部品・修理収入は442億7500万円(同4・2%増)、その他農業関連(施設工事など)は245億7000万円(同3・6%減)となった。
〔海外〕
整地用機械(トラクタ、芝刈機など)は360億3000万円(同8・6%減)、栽培用機械(田植機など)は10億1900万円(同44・2%減)、収穫調製用機械(コンバインなど)は5億8700万円(同56・7%減)、作業機・補修部品・修理収入は69億2700万円(同8・3%増)、その他農業関連は108億2800万円(同37・6%増)となった。
〈今後の見通し〉
次期の売上高は当期比20億7400万円増加の1705億円を見込む。国内市場では構造的な需要の減少傾向が継続する中、成長分野である「大型」「先端」「環境」「畑作」への経営資源の集中や販売強化を図り増加を見込んでいる。海外市場では、北米はコンパクトトラクタ市場の底打ちを見込み増加、欧州は前期にあった仕入れ商品の特需が剥落するものの、高水準を維持、アジアはタイ周辺国への展開と韓国での在庫調整後の出荷促進を見込み増加し、海外全体では売上高の伸長を見込んでいる。
営業利益はプロジェクトZ施策の効果発現などにより当期比6億7900万円増加の26億円を見込む。経常利益は18億円、親会社株主に帰属する当期純利益は13億円を見込んでいる。なお、業績見通しにおける想定為替レートは1米ドル=150円、1ユーロ=157円としている。
◇
〈プロジェクトZの進捗状況〉
▽進捗 短期集中で実行する抜本的構造改革のうち、生産拠点の再編や販売会社の統合など、主要施策の進捗状況は概ね計画通り進んでいる。成長戦略に向け海外では欧州事業の拡充策、国内においては営業組織の再編を実施し成長戦略の基盤つくりを進めた。
▽抜本的構造改革 (1)生産最適化「生産拠点再編」=計画通り進捗。(株)ISEKI M&D(松山)に製品組立を集約すべく建屋新設に着手。(株)ISEKI M&D(熊本)からのコンバイン生産移管プロセスは計画通り進んでいる。生産拠点の再編に係る投資については、生産効率を改善しつつ投資抑制に努め、当初総投資計画460億円から380億円に圧縮した。
(2)開発最適化「製品利益率の改善と開発の効率化」=一部遅延。製品利益率の改善は当初計画より一部遅延しているものの、リソースを追加投入し回復を図る。その改善効果は2025年下期より順次発現し、27年に改善目標の達成を目指す。開発の効率化は削減機種・型式を確定次第、実行しており計画通り進捗している。
(3)国内営業深化「成長戦略への基盤つくり=計画通り進捗。(株)ISEKI Japan設立に伴い営業組織体制を変更。経営資源を集中し迅速な意思決定と強力な推進体制を構築した。
(4)人員構成の最適化と人的資本投資=人員構成の最適化↓一部計画変更。希望退職は募集人員を下回るも、グループ全体の人員計画見直しにより想定していた人件費水準を確保。
人的資本投資↓計画通り進捗。教育、研修プログラムの強化・ダイバーシティ推進採用・成長分野への人材配置を実行。 (5)経費削減=経費削減の取り組みは当初計画より遅れているが、今後は業務仕分けを徹底し、具体的な改善策を実行することで挽回する。
▽成長戦略 (1)海外地域別戦略と商品戦略の展開=計画通り進捗。欧州において英国販売代理店「プレミアム・ターフ・ケア社」を25年1月から連結子会社化(2)国内成長分野への経営資源集中=計画通り進捗。成長分野である「大型」「先端」「畑作」「環境」へ集中・販売強化すべく、(株)ISEKI Japanに「大規模企画室」を設置。
〈資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート)〉
当社のPBR(株価純資産倍率)は1倍を下回る水準が継続しており、24年12月末時点で0・30倍に止まっている。プロジェクトZの諸施策を着実に進めることにより27年までにPBR1倍以上の実現を目指す。
▽目指す姿(2027年) 連結営業利益率=5%以上、ROE(自己資本利益率)8%以上、DOE(株主資本配当率)2%以上。
▽改善の方向性と施策の進捗状況 (1)収益性改善(生産最適化、国内営業深化は計画通り進捗。開発最適化は利益率改善では一部遅延、開発効率化は計画通り。経費削減は一部遅延、業務仕分け徹底)(2)資産効率化(3)成長に向けたキャッシュアロケーション。在庫圧縮により営業キャッシュフロー黒字化(4)IR活動・ESG取り組み強化―など。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
大型・先端技術で記念展/ISEKI Japan関東甲信越 |
|
| |
|
|
| |
(株)ISEKI Japan関東甲信越カンパニー(瀧澤雅彦カンパニー社長)は14〜16の3日間、阿見町(茨城県)の同カンパニー本社敷地内で「大型農機展 ISEKI Japan合併記念アグリフェスタ」を開催した。大型・先端・畑作・環境などの同社グループが掲げる主要ターゲットに即した製品群を敷地いっぱいに並べ、会期中はおよそ5000人の来場農家に最新技術情報を発信した。
駐車場からバスで入場した参観者は、受付後、まずトラクタBF32の出迎えを受け、通路左列に大型のビッグTシリーズT8S(305・9PS)〜ジアスNT365(36PS)、同右列に小型のZ153(15・6PS)〜レスパ5シリーズRTS255(25PS)と、合わせて50台ほどのトラクタ通りを経て、大型作業機、圃場実演、試乗コーナー、スマート農機デモコーナーなどに移動する会場構成とした。
ビッグTシリーズの200PS以上・超大型機を目にする機会が少ない関東地域の農家の中には、座席に乗り込んでビッグの感触を味わい、スマホにその威容を納める向きもあった。また、今回初めて設置した模擬整備場のコーナーでも海外仕様の大型トラクタなどを置き、本州地区にも大型化の波が寄せてきていることを実感させた。
同社担当者は、茨城県ではまだ200、300PSクラスの普及は少ないとしつつ、多目的に使え季節性の少ないトラクタの動向が実績全体を支えると強調、2025年市場におけるトラクタ拡販への意気込みをみせた。加えて中型に当たるBFシリーズについては、名称ばかりでなく真の性能、機能を理解してもらうための活動はまだまだ進めていかなくてはならないとして、今後さらに実演会などに力を入れていく考えだ。
先端技術に関しては、スマート農機関連でアイガモロボ2、ザルビオフィールドマネージャーの施肥マップに連携した田植機、トラクタ、各社の自動操舵システムなどを紹介し、実演では、初日午前はロボット田植機の動きを説明した。
今回のイベントの特徴の1つに、畑作、野菜作関連機械の充実があげられる。耕作面積の大規模化に伴い、作業のスピードアップや作業精度の向上ニーズが高まっているのに応えて、ディスクハロー、パワーハロー、レーザーレベラーをはじめ稲作用でも高速作業をうたう機種展示が目を引いた。また、野菜作機械コーナーでは、畝成型機、畝成型同時マルチ、掘取機などの圃場作業に供する機械から調製、洗浄に至る様々な製品が揃い、地域の特産品ニーズに対応し、きめ細かさで実績を作っているメーカーの声も聞かれた。
他方、連日5、6課題の情報を提供した講習会では、初日午前の「SDGsとスマート農機」と題する公開講座(茨城大学農学部と井関農機などとのコラボ、1回のみ)を皮切りに、新型の低価格自動操舵、ショート・ディスク、アイガモロボ2、脱プラ水稲一発肥料、Jクレジットなど、広範な話題を盛り込み、農家の営農に資した。
このほか、田植機、コンバイン、管理機、稲作用の春・秋製品と、100社を超える協力企業の出展を得て、常にも増して多種多様な商品が揃い、稲作関連コーナーでは、米価格上昇に伴う農家の機械購買意欲の盛り上がりはまだ続いている、色彩選別機はオーダーに応え切れない状況といった声が聞かれた。こうした時流に沿って、会場では需要づくりに向けた「新生ISEKI」のエネルギーが各来場者に照射され、イベント後は各営業所単位のフォロー活動に熱が込められていく。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
水素燃料を活かす/コベルコ建機 |
|
| |
|
|
| |
コベルコ建機(株)(山本明社長・東京都品川区北品川の5の15 大崎ブライトコア5F)は18日、神戸製鋼所とともに、神戸製鋼所高砂製作所に水素燃料電池ショベルの高圧水素充填設備の整備を完了したと発表した。KOBELCOグループが中期経営計画で掲げているカーボンニュートラルへの挑戦の一環で、水素関連技術の研究開発と水素を利活用した製品化・事業化のテーマを具体化した。
コベルコ建機の水素燃料電池ショベル試作機は、広島事業所で基礎評価を完了。今後は2026年度に国内で行われる実証実験での利活用に向け、今年3月以降に高砂製作所で連続掘削作業などの本格稼働評価を実施、水素燃料電池ショベルの現場導入へ取り組みを進めていく。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
決算特別キャンペーン展開/プロフレックス |
|
| |
|
|
| |
プロフレックス(株)(平山哲社長・埼玉県さいたま市見沼区御蔵1172)は3月17日までの間、油圧ホース加締機S2、同切断機EM1Sなどの購入者に対し、10万円(税抜き)を上限に希望のホースや継ぎ手をプレゼントする決算特別キャンペーンを展開している。また、両機種をセットで購入する場合は、合計金額(税抜き)より5%オフの特別価格を設定している。対象機種はほかにホースアッセンブリ機HM200シリーズ、同NISシリーズ、高圧ホース切断機EM3がある。
問い合わせ先は同社R&Dロジスティックセンター、TEL048・687・6222もしくはhttp://www.proflex.co.jp/contact/まで。
ホース専用加締機S2AC(100ボルト)は、油圧ホース/高圧ホースをおよそ10分間で修理・自作できる機械。重機の遊休時間を短縮するのに加え、予備ホースを減らすことができ、ホース関係のコスト半減を可能にする。軽量・コンパクトで移動が簡単、マイクロメーターにより常に高精度の加締め径を維持、オプションでクーラーホースアッセンブリができる―などの特徴をもっている。税込み価格は71万2800円(ダイズパッケージ)。
また、油圧ホース切断機EM1Sは、AC100ボルト対応で、φ25〜35・0メガパスカルホースまで楽々切断でき、切断粉、切断熱を大幅に軽減する。税込み価格は32万7800円、専用台付きは同35万5300円。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
新執行体制を内定/井関農機 |
|
| |
|
|
| |
井関農機(株)(冨安司郎社長)は14日、取締役・監査役の異動、役員の委嘱業務変更並びに2025年3月27日開催予定の定時株主総会日以降の経営体制を発表した。内容は次の通り(敬称略)。 (2025年3月27日付)
〈退任予定取締役〉
▽Executive Senior Adviser(取締役常務執行役員、人事、総合企画、IR・広報担当、コンプライアンス担当)深見雅之
▽常勤監査役(理事開発製造本部副本部長「プロジェクトZ」副リーダー)高橋一真▽監査役(社外監査役)山下泰子
〈退任予定監査役〉
▽常勤監査役 町田正人▽監査役(社外監査役) 平真美
〈役員の委嘱業務の変更(2025年3月27日付)〉
▽人事担当(財務担当)取締役常務執行役員IT企画担当神野修一▽総合企画、IR・広報、財務担当(海外営業本部長)取締役常務執行役員谷一哉▽海外営業本部長(海外営業本部副本部長)執行役員木全良彰
〈2025年3月27日開催予定定時株主総会日以降の経営体制(予定)〉
▽代表取締役社長執行役員=冨安司郎▽代表取締役専務執行役員=小田切元(「プロジェクトZ」リーダー)
▽取締役常務執行役員=神野修一(人事、IT企画担当)▽同常務執行役員=谷一哉(総合企画、IR・広報、財務担当)▽同(社外取締役)=岩崎淳(独立役員)▽同(同)=木曽川栄子(同)▽同(同)=岸本史子
▽常勤監査役(社外監査役)=藤田康二▽同(同)=森本健太郎▽同=高橋一真(新任)▽監査役(社外監査役)=山下泰子(独立役員)(新任)
▽常務執行役員=若梅俊也(海外営業本部副本部長、アジア担当)▽同=粟野徳之(内部監査、総務、コンプライアンス・法務担当)
▽執行役員=渡部勉(開発製造本部長)▽同=石本徳秋(営業本部長、夢ある農業総合研究所担当、(株)ISEKI Japan代表取締役社長)▽同=木全良彰(海外営業本部長)▽同=勝野志郎(商品企画担当)▽同=瀧澤雅彦(営業本部副本部長、(株)ISEKI Japan専務取締役営業統括担当、関東甲信越カンパニー社長)▽同=守屋昭二(海外営業本部副本部長、北米・欧州担当、北米豪州営業部長)▽同=神谷寿(開発製造本部副本部長品質担当)▽同=伊藤勝(総合企画部長)
〈新任監査役候補者の略歴〉
【高橋一真(たかはし・かずま)氏】1964年1月28日生まれ。87年3月同志社大学商学部卒。同年4月井関農機(株)入社、2011年6月財務部長、16年1月執行役員、同年3月総合企画部長、17年1月財務部副担当、19年1月総合企画副担当、同年4月開発製造本部長補佐、20年9月開発製造本部統括役員、22年1月開発製造本部副本部長(現任)、総合企画副担当、23年11月「プロジェクトZ」副リーダー(現任)、25年1月理事(現任)
【山下泰子(やました・やすこ)氏】1963年11月5日生まれ。86年3月慶應義塾大学商学部卒。87年10月監査法人トーマツ入社、2020年5月新日本監査法人入社、13年12月司法書士山下泰子事務所設立(現任)、20年5月イオンモール(株)社外取締役
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
茨城県から女性登用で表彰/スガノ農機 |
|
| |
|
|
| |
スガノ農機(株)(渡邊信夫社長・茨城県稲敷郡美浦村間野天神台300)は、茨城県が実施した令和6年度の「茨城県女性リーダー登用先進企業表彰」で優秀賞を受賞した。14日午後に水戸市のザ・ヒロサワ・シティ会館で表彰式が行われ、大井川和彦知事より表彰状を授与された渡邊社長は、今後も優秀な人材の活躍を期すべく率先して性別、国籍などに関わらない採用、登用、育成を進めていく意向を示した。
同表彰制度は、女性の登用に積極的に取り組み、その実績が優れている企業を顕彰するもので、表彰式は「女性活躍・働き方応援シンポジウム」の冒頭に行われた。 初めに挨拶した大井川知事は、他県と比べて企業における女性の管理職割合が低く、平均勤続年数の男女間格差が大きい県内事情を報告し、各表彰企業の対応、努力に敬意を表しつつ、これからの社会は全ての人が活躍できる環境を作らなければ生き残っていくことはできないと指摘。そのための施策推進にしっかりと取り組んでいきたいと述べた。
引き続き各表彰企業の取り組みを紹介し、スガノ農機は(1)年齢・性別によらない管理職登用(2)定期的なジョブローテーションによる人材育成(管理者候補)(3)トップ主導による女性活躍に対する意識の醸成(4)法定日数を上回る育児・介護休暇制度の導入―などを進め、女性課長の活躍、係長比率が2022年の22%から2024年は45%に向上しているなどの具体的な実績に結びつけている点が高く評価された。
同シンポジウムでは、県ダイバーシティ推進センター関係者によるダイバーシティ&インクルージョン講話およびジャーナリストの福島敦子氏による講演「ダイバーシティと企業価値向上〜企業の持続的成長を実現させる鍵〜」が行われた。
会場で渡邊社長は、「我が社は仕事の上で性差は全くない、同じ条件下で働いており、すでに要職にある女性が現場を回している。また、各セクションの連携、協力体制が出来上がっている」と話し、実力本位で個人の業務を評価、人事にも活かしている現状を説明した。
今回の受賞で、同社の取り組みがさらに広く認知され、優秀な人材の確保・育成、あるいは業績アップに結びつくことが期待される。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
全国800カ所の気温データ取得/バイエル |
|
| |
|
|
| |
バイエル クロップサイエンス(株)(大島美紀社長・東京都千代田区丸の内1の6の5)はこのほど、雑草の発生状況に合わせて最適な除草剤の処方提案をサポートするウェブアプリケーション「my防除」で取得する気温データの気象観測地点を、47カ所から全国約800カ所に拡大した。
「my防除」は、雑草の発生状況に基づき適切な薬剤(有効成分)、薬量、散布時期の処方提案を通じて最適防除を実現する、「水田雑草テーラーメイド防除」の核となるアプリ。
散布適期を算出する際に使用する気温データを全国800カ所の気象観測地点に拡大したことで、近年気候変動による天候変化が課題となる中、圃場のある地域の気象条件や除草課題に、より適した高精度のテーラーメイド処方が可能になる。また、経年データの蓄積により「my防除」では2025年度から、問診時に選択できる水田雑草の草種を拡充し、シズイや雑草イネなどの難防除雑草についても最適な処方提案が可能になった。一部地域では、田植同時処理除草剤(粒剤)との体系除草処方の実装も開始した。
さらに、水田中干し延長時における雑草防除を最適化する処方を実装するなど、農家の作業の効率化と環境負荷低減の両面から、常に機能や利便性の向上を行っている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
コフナの普及図る/コフナ農法普及協議会が総会 |
|
| |
|
|
| |
コフナ農法普及協議会(事務局:ニチモウ(株)・東京都品川区東品川2の2の20)は14日、東京都品川区のアワーズイン阪急で令和7年通常総会を開いた。これには、生産者や販売代理店、流通業者、資材メーカーなど約50人が参加した。
開会に当たり、挨拶に立った諏訪貴省会長は「植物のフィジカルは根に宿っている。エネルギーをもった植物を育てることによって収益を確保できる。コフナ農法がどんな価値を農家に届けることができるのか、意見交換しながら考えていきたい」と力強く語った。
続いてニチモウ執行役員機械・資材事業本部長の福井豊氏が「ニチモウは豊かで健康な暮らしづくりを支えることをテーマに取り組んでいる。農家の皆様のためにコフナの普及に尽力していく」と挨拶した。
次にコフナ農法の優良生産者表彰があり、岐阜県高山市でトマトを生産している森本守氏と、佐賀県みやき町の(有)みやき肥料代表の大庭英誉氏に表彰状が贈られた。
基調講演では、東京農業大学の加藤拓教授が「畑・水田の重要要素 腐植について」と題して講演した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
売上収益は872億円/バンドー化学・2025年3月期第3四半期連結決算 |
|
| |
|
|
| |
バンドー化学(植野富夫社長・兵庫県神戸市中央区港島南町4の6の6)は10日、2025年3月期第3四半期の連結決算を発表した。これによると、売上収益は872億7500万円(前年同期比8・1%増)だった。また、コア営業利益は57億7900万円(同1・9%減)、営業利益は59億9400万円(同13・3%減)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は42億4200万円(同15・0%減)となった。事業(セグメント)別でみると、自動車部品事業の売上収益は439億6200万円(前年同期比10・9%増)、セグメント利益は34億4600万円(同15・9%増)だった。
国内の同事業は、自動車生産台数減少の影響を受けた。一方、輸出向け製品は好調に推移し、販売が増加した。海外は、米国で補修市場向け製品の販売が増加。また、中国・アジアでは二輪車メーカーの生産が回復、スクーター用変速ベルトなどの販売が増加した。
産業資材事業の売上収益は286億5500万円(前年同期比5・1%増)、セグメント利益は19億5100万円(同27・9%減)となった。同事業の一般産業用伝動ベルトは、国内で産業機械用伝動ベルトの販売が前年並みに推移。海外では欧米で産業機械用伝動ベルトの販売が増加、中国・アジアにおいても農業機械用伝動ベルトの販売が増加した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
再生エネや脱炭素化/スマートエネルギーWEEKから |
|
| |
|
|
| |
再生可能エネルギーや脱炭素化を促す各種製品・技術情報を集めた第23回スマートエネルギーWEEKが19〜21日の3日間、東京ビッグサイトで開かれ、新エネルギーの総合展というサブタイトル通り、これからの生活、産業全般を大きく定義づけるイベントとあって、内外からの数多くの参観者で賑わいをみせた。業界からも木質バイオマス関連、太陽光発電業界の労働負担軽減に貢献する草刈機、また、農業分野における脱炭素化促進に貢献する技術・システムなどを有する企業がその存在をアピールした。ここでは各社の出展概要をみた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
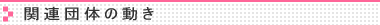 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
スマート農業を推進/農業システム化研究会が最終成績検討会 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人全国農業改良普及支援協会(岩元明久会長)は18、19の両日、都内のアルカディア市ヶ谷で、令和6年度全国農業システム化研究会最終成績検討会を開催し、6年度の共通テーマ「イノベーションによる農業の生産力向上と持続性の両立を目指した実証」の成績発表が行われた。開会式では、「スマート農業技術活用促進に向けた研究開発」と題し、農研機構農業機械研究部門の長崎裕司所長の講演が行われた。
開会式では、岩元会長が、「食料・農業・農村基本法の改正など農政の新たな動きに対応し、システム化研の仕組みを活かしながら、スマート農業など重要課題に取り組んでいきたい」とあいさつした。
来賓として、農林水産省農産局の吉田剛技術普及課長と、(株)クボタ取締役専務執行役員機械事業本部の木村浩人副本部長がそれぞれあいさつ。農林水産省の吉田課長は、近年の気候変動や環境負荷低減の対応などで、技術への期待が高まっているとし、「現在、協同農業普及事業の運営指針の改正作業を行っており、技術の現場導入に向けて、普及組織、メーカーなど官民が協力して取り組んでいかなければならない」と、スマート農業などに対応した普及事業の重要性を述べた。
クボタの木村専務執行役員は、スマート技術で農業に貢献していくとし、(1)オートノマス(ロボット農機)(2)コネクテッド(KSAS)(3)カーボンニュートラル―の新規課題に取り組み、農業を魅力ある産業に変革していきたいと意欲を示した。
農機研の長崎所長による講演では、農機OPENAPIの取り組み、両正条田植機の開発、スマート農機に適合した品種・栽培技術などが紹介された。
成績発表は、第1分科会が「スマート農業技術による稲作経営の確立に関する実証調査」、「水田における土地利用型作物等の生産効率向上に関する実証調査」。第2分科会が「野菜等の効率的生産技術に関する実証調査」、「大豆の安定生産に関する実証調査(大豆新技術等普及展開事業)」、「効率的な病害虫雑草防除技術に関する実証調査」。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
出荷は3595億円/日農工・2024年動態実績 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本農業機械工業会(増田長盛会長)はこのほど、経済産業省生産動態統計に基づく農業機械生産出荷実績の2024年1〜12月分を取りまとめて発表した。
それによると、2024年通期の累計生産金額は3582億5800万円で前年同期比84・8%、累計出荷金額は3594億6000万円で同90・3%となり、どちらも落ち込んだ。
12月単体の実績では、生産額は255億9500万円で同89・8%、出荷額は249億9000万円で同84・2%に減少した。
機種別で2024年の累計出荷実績をみると、機種によって明暗が分かれた。トラクタは数量が9万1776台で前年同期比79・4%、金額は2066億2700万円で同84・7%に減少した。内訳をみると、20PS未満は5262台(前年同期比86・1%)で65億7400万円(同105・0%)と金額は増加。20〜30PSは2万8361台(同92・1%)で377億7200万円(同97・9%)。30PS以上は5万8153台(同73・9%)で1622億8100万円(同81・5%)となっており、大型機の減少が目立った。
動力耕うん機は、8万7540台(同78・7%)で108億7900万円(同85・2%)に落ち込んだ。田植機は1万3790台(同85・9%)で281億3500万円(同90・3%)に減少。コンバインは1万1274台(同95・5%)で692億5000万円(同101・5%)となり、金額のみ増加した。
一方、刈払機も59万3428台(同94・3%)で128億2100万円(同96・5%)に減少した。防除機は9万9035台(同98・8%)で53億400万円(同115・1%)、籾すり機は8091台(同93・5%)で55億8200万円(同113・9%)とどちらも金額が2桁増。乾燥機は1万822台(同88・7%)で136億7900万円(同97・4%)になった。精米麦機は1万952台(同105・9%)で71億8300万円(同136・4%)に増加した。米価の値上がりを受け、収穫調製用機械や穀物処理機械が好調であった。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
秋元真夏さんがJAタウン新CM/JA全農 |
|
| |
|
|
| |
JA全農は、2月13日から3月18日の期間、産地直送通販サイト「JAタウン」において、毎年好評を博している「年度末大決算セール」を開催する。これに併せ、「JAタウンオフィシャルサポーター」の秋元真夏さんが出演する「JAタウン新CM」を制作し、地上波テレビ(関東地区)、TVer、YouTubeなどで放映する。
期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品約5500点以上が20%OFFで購入できる。対象商品の数は過去最大規模で、各産地自慢の米や肉、野菜ボックスなどの他、旬の果物や海産物、加工品など豊富なラインアップを取り揃えている。
また、全国各地の和牛商品を対象とした「和牛を食べようキャンペーン」も2月28日まで実施している。
「JAタウン」は、全農が運営するECサイトで、「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「JAタウン」に出店する全国の農協などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品をインターネットを通じて消費者に直接届ける産地直送通販サイト。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
GAPで持続的生産/日本生産者GAP協会がシンポジウム開催 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本生産者GAP協会(田上隆一理事長)は2月20、21の両日、茨城県つくば市のつくば研究支援センター及びWebで2024年度GAPシンポジウムを開催した。「世界のGAP先進地スペイン・アルメリア農業に学ぶ―ヨーロッパ随一の園芸産地アルメリアはスマートで持続可能な農業―」をテーマに掲げ、家族経営農家に対するGAP指導で欧州随一の野菜産地となったアルメリア農業について、GAP視察ツアー参加者による報告など様々な角度から話題提供し、今後の日本農業の発展について議論を深めた。
開会挨拶した二宮正士常務理事は、先般改正された食料・農業・農村基本法について(1)食料安全保障(2)環境と調和(3)生産性向上(4)農村の振興を柱としており、数十年先を見据えた政策が明文化されたことは画期的だと評価。一方で、同法に頻出するキーワード「持続性」について、環境調和や収益性、労働力など様々な意味があることから、それらの折り合いをつけた全体最適化が必要であり、その理想の姿に向けて長いプロセスを辿り成功させたのが今回学ぶアルメリア農業だと指摘。日本農業の持続性実現に向け、どうプロセスを進めていくか素晴らしい教科書になると語った。
続いてスペイン大使館経済商務部・内田瑞子氏が来賓挨拶を行い、スペインはEU加盟後のこの40年で劇的な経済成長を遂げ、基幹産業の農業は輸出全体の2割を占めると述べ、国が国際競争力を高めるための国家戦略として農・食のバリューチェーン化を後押ししているなどと紹介した。
講演の一部をみると、田上理事長は「アルメリア農業の進化 GAPにおける農協と自治体の介入」を講演した。世界のGAPステージがSDGsと同期し、持続可能性を目指すものに移行したことから、世界のGAP先進地であるアルメリア農業に学ぶところが大きいとした。同地区の温室面積は約3・3万ヘクタールで、約1・5万戸の家族経営農家がトマト、キュウリ、ナスなど多様な野菜を栽培。同地区の温室は環境制御装置等でハイテク化され、廃プラ対策や海水淡水化といった環境問題にも取り組んでいるという。同地区の農業経営の特徴として、地方自治体など行政によるGAPへの介入、小規模家族経営が集まった農協組織の発達、農業技術者(テクニコ)の役割が大きいことなどを示し、GAP認証取得をはじめ、有機農業、輸出などが進められている状況等を紹介した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
施設供用の第1弾を発表/農研機構 |
|
| |
|
|
| |
農研機構は19日、同機構が供用する茨城県つくば市の圃場において、(株)NTT e―Drone Technology(以下、NTTeドローン社)がドローンの飛行試験を開始したことを発表した。スマート農業技術活用促進法による施設供用第1弾にあたる。
同機構は昨年10月に施行された「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」に基づき、10月1日より圃場やスマート農機の供用をスタートしている。NTTグループのドローン専業会社であるNTTeドローン社は、同法に基づいて開発供給実施計画の認定を農林水産省より受けており、このたび農研機構と利用契約を締結し、供用圃場の利用を開始したもの。今回の同計画では、傾斜地のカンキツ防除における労働時間の削減や、衛星やドローンで取得したセンシング結果に連動した可変施肥等による作業の効率化及び環境負荷の低減に寄与する国産大型ドローンの供給を目指しており、この1月8日から供用圃場を活用してドローンの開発・改良試験を開始した。可変施肥等の精度の向上に向けて、同機構の圃場で実証データの収集を行っている。
農研機構は今後もスマート農業技術活用促進法に基づく供用施設等を拡充し、技術開発と普及の促進に寄与していくとしている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
タンザニア農業スタディツアーWeb説明会開催/AFICAT |
|
| |
|
|
| |
JICAが推進するAFICAT(日・アフリカ農業イノベーションセンター)事業において、6月29〜7月6日、本邦企業向けタンザニア国スタディツアー(農業分野)が実施される。実施に先立ち、3月5日午後4時より、同ツアーの概要を紹介するオンライン説明会が行われる。
AFICATはJICAが推進し、アフリカ諸国における先進農業技術の導入促進を官民連携で実施する事業。日本の農業資機材メーカーのアフリカ進出を支援しており、2022年2月からタンザニア・コートジボワール・ナイジェリア・ガーナ・ケニアの重点対象5カ国にて順次稼働し、昨年2月より新フェーズとして引き続き活動している。
同事業の一環として今夏行われるスタディツアーは、タンザニアのキリマンジャロからダルエスサラームを訪問し、同国の農業現場を視察。訪問場所や面談相手は▽農家・農業機械所有者・圃場▽タンザニア国際見本市▽JICA/農業省機械化局長との協議▽その他農業機械代理店、農業資機材販売店など―を想定し、参加者の希望により可能な範囲で調整予定。ツアー対象者は国内の農業資機材メーカー、農業関連企業などで、参加者数は5〜20名程度としている。現地のキリマンジャロ集合、ダルエスサラーム解散。募集締切は第1次が4月11日、第2次が5月30日を予定。
3月5日の説明会では、タンザニア国農業機械化の現状やスタディツアー訪問先候補地の紹介、同ツアー募集要項の説明、質疑応答などが行われる。説明会対象者はタンザニア進出またはAFICAT活用の可能性がある国内企業等や、タンザニア国の農業・稲作・機械化事情などに関心があり現地を見分したい国内企業等。参加費無料、定員100名。申し込みは3月3日までに参加申し込みフォーム(https://forms.office.com/r/iAhLXXrvuU)から。問い合わせは(株)かいはつマネジメント・コンサルティングAFICAT調査チーム(aficat.team@kmcinc.co.jp)まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
千葉大で第60回年次大会/関東農業食料工学会 |
|
| |
|
|
| |
関東農業食料工学会(北村豊会長)は15日、千葉県松戸市の千葉大学松戸キャンパスにおいて、2024年度関東農業食料工学会第60回年次大会を開催した。関東地区の大学や研究機関、企業など会員による最新の農・食に関する研究成果が口頭発表されたほか、学会創基60周年記念セミナーや、若手研究者向けの初学の会などが行われた。また、昨年に続き、今回も同会場にて、農業施設学会による2025年農業施設学会学生・若手研究発表会(ポスター発表会)が同時開催され、両学会の会員や学生らがお互いに交流を深めていた。
関東農業食料工学会の口頭発表では、農業機械関連については(1)圃場整備事業における収益拡大に向けた効率的な機械運用(宇都宮大学)(2)水稲移植作業における圃場内作業時間低減を目指した圃場条件(同)(3)ゴム履帯車両の後進畦畔乗り越え時の挙動に関する研究(同)(4)農業機械の乗降安全性向上に関する研究(同)(5)農業スマート安全のためのモデルベースアプローチ(東京農工大学)(6)アルキメディアンスクリューを用いた水陸全方位移動ロボットの開発(同)(7)自律走行型害獣追払いロボットの開発(東京大学など)(8)GTAP―BIOモデルによるバイオ燃料生産時のILUCの算出(東京大学)(9)荷馬車による発電(同)―が行われた。
そのうち(5)は東京農工大学の酒井憲司特任教授が研究発表。酒井氏はトラクタ横転事象について、モーション型ドライブシミュレータによる可視化により事故体験者の体験・知見を顕在化し、社会的認識を形成する研究を進めており、これをトラクタ横転に対するモデルベース開発(MBD)と位置付けていると説明。酒井氏は現時点で1604件のシミュレーション結果を動画にしてWeb公開しており、これらのトラクタ横転シナリオの分類を試行した。分類として共振ジャンプ現象や入退出路横転、旋回時横転、前輪脱輪横転、片ブレーキによるダッシング発生などを提示。
さらに事故体験者への聞き取りも行い、現場検証とシミュレーションを比較した。事故事例のシナリオ再現をしたところ、急傾斜登坂時の横滑り横転において、航路設定のわずかな違いにより無事登坂できたことから、事故は運転の上手さや操作の誤りではなく確率の問題として起きているのではないかと指摘。正しい運転を定義するよりも、事故の臨界領域を理解し、予防するアクティブセーフティの考え方が重要などと語った。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
AI農業が人類救う/関東農業食料工学会が初学の会 |
|
| |
|
|
| |
関東農業食料工学会(北村豊会長)は15日、千葉県松戸市の千葉大学松戸キャンパスで開催した2024年度関東農業食料工学会第60回年次大会において、初学の会を実施した。
これは農業企業関係者を講師に招き、若手研究者や学生に向けて、業界のトレンドや今後の展望を伝えるもので、今回はAGRIST(株)営業部新規事業開発責任者・尾身喜信氏が「AI農業で人類を救う―AIとロボットを使ったスマート農業」を講演。農業を儲かる産業にしていく同社の取り組みを紹介した。
尾身氏によると、同社は宮崎・鹿児島・茨城の3地区を拠点に、ピーマンやキュウリの自動収穫ロボットをはじめ、AIとロボットを使ったスマート農業を全国に展開しているスタートアップ。地域密着型でテクノロジーを活用した農業生産を進めており、技術の高さと社会課題解決の取り組みが高く評価され、2019年設立からわずか5年で国内外の20以上の賞を受賞している。宮崎・鹿児島では約1ヘクタール規模の自社農場を構え、事業連携でピーマン等の生産を実施。収穫ロボットの稼働と栽培環境データ管理を行い、高収量を目指す取り組みなどを行っている。
昨今の取り組みでは、マイクロソフトの支援を受けて「AGRIST Ai」を開発。これは農業に特化したAIで、高精度な収量予測を行い、栽培管理を支援するシステム。同AIはロボットやセンサーで収集したデータを分析して、営農に役立つレコメンドを提示。収量や売り上げ、栽培記録、物流、環境データの見える化・管理はもちろん、物流・小売りなどと連携して需要に合わせた最適出荷を行え、ドライバー不足や食品ロスなどにも対応する。また、農場5〜6年分のデータを入れると毎週の収量予測を誤差20%で推論し、作業者や作業時間、出荷の管理判断に役立つと述べ、将来的にはWAGRIなど用いて市況価格予測もしたいという。
今後については、ロボットとAIを用いて農業全体をDX化していき、事業連携で産業と雇用を作っていくと展望。自社農場10ヘクタールと民間農場90ヘクタールを合わせた100ヘクタールで100億円を目指すなどと語った。
講演の後、質疑応答が行われ、参加した学生らと盛んに情報交換をしていた。「画像データをどのように活用し展開していくか」の質問には「今は収量予測など生育が主で、一部害虫発見にも活用している。今後は光合成促進や非接触の水分量の分析も検討。水分量は収穫後の品質保持にも使えるのではとの意見もあるが、まだ実証段階」などと応答していた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
農機の今後10年を展望/関東農業食料工学会大会から |
|
| |
|
|
| |
関東農業食料工学会(北村豊会長)が15日に千葉大学松戸キャンパスで開催した2024年度関東農業食料工学会第60回年次大会から、学会創基60周年記念セミナーの一部概要をみる。
冒頭、挨拶した北村会長は、「学会創基60周年にあたり、農業食料工学の研究・開発における過去10年の歩みと未来の10年を展望する講演会だ」と同セミナーの趣旨を紹介し、「講師は皆それぞれ研究、実業の分野で活躍してきた3名であり、これからの10年について希望をもって迎えられる話を聞けるので楽しみにしてほしい」と期待を寄せた。
セミナーでは、農研機構農業機械研究部門所長・長崎裕司氏による「農業食料工学の10年の歩みと未来展望〜農機研の取組を通して〜」、筑波大学生命環境系准教授・トファエル アハメド氏による「農業食料工学の10年の歩みと未来展望」、JA全農施設農住部・土方享氏による「農業共同利用施設の設置運営の将来を考える(施設の計画・設置・運営にかかわる課題と展望)」の3講演と質疑応答が行われた。
長崎氏は農研機構農業機械研究部門(農機研)も2022年に設立60年を迎えたとし、農機研の取り組みとして、スマート農機開発を中心としたこれまでの10年の歩みと、今後の方向性について紹介。農機研の主な業務は設立から60年にわたり農業機械の開発改良、農作業安全・検査業務、国際標準化と変わっていないとし、この10年における取り組み例として、2022年度にIHIアグリテックと共同開発したリモコン式小型ハンマーナイフ草刈機を示した。
また、近年の大きな流れとして、研究開発に係る2施策である(1)みどりの食料システム戦略(2)スマート農業技術活用促進法が出されたことをあげ、これらは農機研のミッションである「生産性向上と環境保全の両立に寄与する農業機械の開発・現場実装及び事故ゼロに向けた農作業安全システムの構築」に一致すると説明。我が国が目指すSociety 5・0を実現するべく、ICTを活用したスマート農業を推進しているとし、水田農業におけるICT技術の取り組み例として、田植え作業と苗補給を1人で実現可能な自動運転田植機や、両正条田植機などを紹介した。
一方で、スマート農業技術については期待が大きい反面、他社間データ連携がされておらず使いづらいなどの声もあり、農機メーカーによる農機APIの実装・公開も進めているなどと述べた。
今後の方向性としては、生産性向上と持続性の両立に向けて、農・食産業向けのAIとロボット技術を活用したスマート農業技術の開発を進めることが重要であり、多様なプレーヤーと連携して、農業を強い産業にし、Society 5・0を実現していくと語った。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
小売団体に文書送付/野菜流通カット協など |
|
| |
|
|
| |
野菜流通カット協議会(木村幸雄会長)は10日、「野菜価格および各種コスト高騰等のご理解とご協力のお願い」と題した文書を小売団体事務局5団体(日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会、日本フードサービス協会、オール日本スーパーマーケット協会)に送付した。一般社団法人日本野菜協会、一般社団法人日本総菜協会と連名。
これまで価格が据え置きの傾向にあったカット野菜やカップサラダにおいて、昨今の野菜・物価高騰等の打撃が甚だしく、自社努力だけでは限界の様相になっていることから、この対応について小売り事業者に対して理解・協力を求める内容となっている。文書を送付した3団体では、各団体会員へ文書を共有し、会員各社における営業ツールとして活用するよう要請している。
送付した文書の概要は次の通り。
昨今の野菜価格およびコスト高騰等に関しまして、下記の通りご理解とご協力をお願い申し上げます。
〇昨今の物価変動等による、様々な直接費及び間接費のコスト増に関しては、会員各社で吸収すべく努力を行ってきたところですが、自助努力だけでは限界があり、各社対応に苦慮している状況でございます。特に、カット野菜やカップサラダは、加工度が少ない生鮮野菜同様の性質を持つものであり、猛暑等の気候変動の影響による野菜原料価格の高騰により、致命的な打撃を受けているところです。
〇コスト高騰や原料価格の変動等への対応は、会員各社が各々の判断で対処することであり、協議会や協会が関与することではございませんが、様々なコスト増や原料価格変動等の事情は会員各社の共通の問題でもありますので、何卒事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。
このような状況でございますので、小売事業者様の許へ会員各社がお伺いした際は、次のようなご対応を賜りたく存じます。
(1)会員各社の事情をお聞きいただき、標記の問題に対し格段のご高配を賜りたくお願い申し上げます。(2)会員各社が価格変更等のご協力のお願いに伺った際には、善処いただきますようお願い申し上げます。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
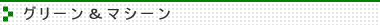 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
鳥取JLCを公認大会に/JLC実行委員会 |
|
| |
|
|
| |
全国のチェンソーの使い手たちが技術を競い合うJLCを主催する日本伐木チャンピオンシップ実行委員会(中崎和久委員長・事務局=全国森林組合連合会内)はこのほど、今年の10月18、19の両日、鳥取県鳥取市福部町の鳥取砂丘オアシス広場で開かれる第4回日本伐木チャンピオンシップin鳥取を第36回世界伐木チャンピオンシップ(WLC)に出場する日本代表選手の選考を兼ねた大会として公認したと発表した。WLCに出場する日本代表選手を選出する大会が青森市以外で開かれるのは今回が初めて。選手を受け入れる鳥取県では、実行委員会(事務局・公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団)を設けて、ホームページを立ち上げるなど準備を本格化、選手募集などの情報発信を行っていく。
日本伐木チャンピオンシップ(JLC)は、チェンソーによる安全で正確な伐木技術の普及を図ろうと2014年に第1回大会が青森県青森市のモヤヒルズで開催されたのが始まり。同年、もしくは翌年に開催される世界伐木チャンピオンシップ(WLC)に派遣する日本代表選手を選考する場として、林業に従事するチェンソーマン達の目標の場となっている。
当初20名強の参加者で始まったJLCは回を重ねるごとに選手数や大会のボリュームもアップ。2020年の第4回大会からプロフェッショナルクラスに加えて、U―24のジュニアやレディース部門も加わるなど、厚みを増してきた。
そして今回、JLCを主催・運営してきた日本伐木チャンピオンシップ実行委員会は、これまで鳥取県内で開催されてきた「日本伐木チャンピオンシップin鳥取」を日本代表選手選考を兼ねた大会として公認。これにより令和8年3月にスロベニアで開催される第36回WLCに出場する日本代表選手選考を兼ねたJLCは今回、鳥取での大会で行うこととなった。これまで5回の歴史を重ねてきたJLCだが、大会を主導してきた青森県以外での初めての大会、試みとなる。
第4回日本伐木チャンピオンシップin鳥取は、10月18、19の両日、鳥取市内の鳥取砂丘オアシス広場を会場に開かれる。鳥取県では、県森連を中心としてこれまで令和元年(2019年)の第1回大会を「日本伐木チャンピオンシップin鳥取」として開催以来、2021年に第2回、2023年に第3回大会を行っており、実績を積んできた。今回、「色んな地域で開催されるようになれば。大会そのものをブラッシュアップしていきたい」という運営委員会サイドの思いもあって、鳥取でのJLCを日本代表選手の選考を兼ねる公認大会とした。
選手を受け入れる鳥取県では、既に県庁のホームページに大会のコーナーを設けた他、公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団を事務局とする「第4回日本伐木チャンピオンシップin鳥取」実行員会を立ち上げ、ホームページでの情報提供をスタートさせるなど開催に向けての準備を進めている。
参加選手と競技種目は、前回の青森での第5回JLCと同様。プロフェッショナル60名、U―24のジュニア10名、レディース10名で実施。競技種目は、WLCのルールに準じた5種目となっている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
チップ化で現場実証/木質バイオマスエネルギー協会 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会(JWBA=酒井秀夫会長)は、2月19〜21の3日間、都内有明の東京ビッグサイトで開催された第10回国際バイオマス展会場で林野庁事業成果報告セミナーを実施、20、21の両日にわたり、最新の木質バイオマス関連の技術情報を提供した。
同協会がセミナーで取り上げた演題は、(1)林地残材の燃料材利用のための作業システムの提案(JWBA)(2)木質バイオマス熱利用プラットフォーム(WOOD BIO)の紹介(同)(3)寒冷地に適した小型薪ボイラーシステムの開発((株)森の仲間たち)(4)皆伐再造林と連動した枝条残材チップ製造・供給システムの開発(フェーズ2)(一般社団法人ゼロエミやまなし)。
「林地残材の燃料利用のための作業システムの提案」は、福井県の坂井森林組合と福島県の真名畑林業(株)を調査対象に、作業工程の整理や各収集システムのコスト試算などとともに、モデル的な林地残材収集システムの設計に取り組んだもの。チップの生産場所から4パターンを設定し、各収集システムの作業、生産量、コスト、条件などを得た。
事業の成果の普及のため今回、「林地残材利用コストガイドブック」を作成し、セミナー会場で配布した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
25年度は通年で横ばい/日本建設機械工業会が需要予測 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本建設機械工業会(山本明会長)は18日、東京都千代田区の経団連会館で会長記者会見を開き、建設機械需要予測(2025年2月公表分)を発表した。
調査対象期間は24年度下期と25年度上下期の3期。対象機種はトラクタ、油圧ショベル、ミニショベル、建設用クレーン、道路機械、コンクリート機械、基礎機械、油圧ブレーカ・油圧圧砕機、その他建設機械の9機種。
発表によると、24年度は国内・輸出ともに減少に転じ、24年度通年の出荷金額は2兆9690億円(前年度比11%減)となり、全体では4年ぶりの減少と予測される。
25年度は下期より緩やかに回復に転じるものの、国内・輸出ともに前年並みに推移し、25年度通年の出荷金額は、2兆9714億円(前年度比±0%)と予測。
〈国内〉
24年度は金利上昇による設備投資意欲低下等により、レンタル向けの出荷が減少すると予測。上期はトラクタが前年同期比4%、建設用クレーンが同5%それぞれ増加するなど3機種が増加したものの、他6機種が減少し、4420億円(前年同期比6%減少)となった。下期は建設用クレーン、油圧ブレーカ・圧砕機の2機種が増加するものの、他7機種が減少となり、4905億円(前年同期比6%減少)と見込まれる。
この結果、24年度通年では9325億円(前年度比6%減少)となり、4年ぶりで減少すると予測される。昨年8月の予測と比較して425億円下方修正となった。
25年度は公共投資等に支えられ、横ばいと予測。上期は4機種が増加もしくは横ばいとなるものの、5機種が減少となり、4393億円(前年同期比1%減)と予測される。下期は6機種が増加もしくは横ばいとなり、4907億円(前年同期比±0%)と予測される。
この結果、25年度通年では、9300億円(前年度比±0%)と予測される。昨年8月の予測と比較して414億円下方修正となった。
〈輸出〉
24年度は、上期は主力機種である油圧ショベルが前年同期比28%減少するなど5機種で減少し、1兆222億円(前年同期比14%減)となった。下期は7機種で減少し、1兆144億円(前年同期比12%減)と見込まれる。
この結果、24年度通年では、2兆366億円(前年度比13%減)となり、4年ぶりで減少すると予測される。
25年度は金利も落ち着き、ミニショベル等が増加に転じ、下期より緩やかに回復すると予測。この結果、25年度通年では、2兆414億円(前年度比±0%)と予測される。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
デジタル林業へ手応え/躍進2025林業機械7 |
|
| |
|
|
| |
令和6年度の林業イノベーション現場実装シンポジウムでは、「〜新技術が拓く林業の未来〜」をテーマに現在、現場での対応が図られている自動化・遠隔操作化に向けた機械開発やデジタル林業の現状を確認した。「林業のデジタル化はどこまで来たか」をメーンテーマにした2日目のシンポジウムは、戦略拠点としてデジタル技術をフル活用する「デジタル林業」の取り組みを進める北海道、静岡、鳥取の3地域の報告などから現在の進捗状況や今後の課題などを共有した。
2日目のシンポジウムで林野庁が令和5年度から進めている「デジタル林業戦略拠点構築推進事業」の事業実施主体として報告したのは、デジタル林業の実践に取り組んでいる次の3地域。
北海道のスマート林業EZOモデル構築協議会、静岡県東部地域デジタル林業推進コンソーシアム、そして鳥取県デジタル林業コンソーシアムで、それぞれ北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課主査の田中君祐氏、静岡県森林・林業局森林計画課主査の山上達也氏、鳥取県森林組合連合会事業部長兼販売事業課長の古都誠司氏が事業報告にあたった。
令和2年度の北海道スマート林業推進方針の策定を受け、同年度から4年度の3カ年に、航空レーザ計測データの成長量予測精度や、ICTハーベスタの基本設計の確認をはじめ、各種機器の計測精度の検証、人力検知作業の省力効果、ICTハーベスタを活用した作業システムによる生産性コスト削減や収益性向上の検証など、各種実証に取り組んだスマート林業EZOモデル構築協議会は、令和5年度から林野庁の新規事業としてスタートした「デジタル林業戦略拠点構築推進事業」に選定され、取組内容を進化させた。
取り組み開始から5年目となる6年度は、枝幸町を実証地として、トラック単位でのデジタルデータによる流通・受入、ハーベスタの生産データを流通に活用できる作業、生産管理の実現などを進めた。
その結果、従来の木材流通に比べデジタル林業では、生産情報のリードタイムの短縮をはじめ、生産情報の精度向上、歩留まり向上・在庫圧縮、すなわち無駄の少ない木材生産が行われるようになったという。
また、静岡県の東部地域におけるデジタル戦略拠点とすべく立ち上げられた同推進コンソーシアムでは、生産情報共有システムを開発。山土場情報を作業員がタブレットに入力することで、県森連は事務所にいながら山土場情報の把握が可能となるもので、立方メートル当たり213円の削減効果が得られたという。
「土場での滞留時間の減少により伐採現場から土場への小運搬も遅滞なく円滑に行えることから、素材生産量の増加にもつながる見込み」と手応えをつかんでいる。この他にも、原木検収・丸太納品情報共有システムを導入、「納材書入力作業」や月末の「請求書内容作業」の省力化が見込まれる。
森林施業プラン支援システムの導入や川上・川中・川下の生産流通SCM(サプライチェーンマネジメント)システムの構築を目標に取り組んだ鳥取県デジタル林業コンソーシアムは、一括した電子処理の確立を目指した。シンポジウムではSCMシステムの構築について報告した。迅速な情報共有・連携を行うことで事務コストを削減した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
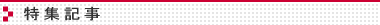 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
RTK局整いスマート農業拡充/福島県特集 |
|
| |
|
|
| |
2011年の東日本大震災から今年で14年となる福島県。地震と原発事故で農林水産業は甚大な被害を受けたが、原子力被災12市町村における営農再開率は2023年度末時点で約45%と少しずつ前進している。今年4月から県内一円でRTK基地局の本格運用が開始される。担い手の減少・高齢化が進む中、省力化・効率化による経営規模拡大、技術継承、収量・品質向上のためにスマート農機の導入は欠かせず、導入経営体数が飛躍的に増加している。さらなる普及拡大に向け、県や各社は様々な取り組みを進めている。大寒波の到来で雪が降る中、各販売店や関係機関を訪ね、福島県農業の農機流通動向を取材した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
市場の概況:農業総産出額1970億円/福島県特集 |
|
| |
|
|
| |
福島県は東北地方の最南端に位置し、県土面積は1万3784平方キロメートルで北海道、岩手県に次いで全国第3位の広さを有する。中央部の奥羽山脈と東部の阿武隈高地の2つの山系が存在するため、山系で隔てられた各地域は会津地方、中通り地方、浜通り地方の3地域に大別される。
会津地方は寒暖の差が大きく、山間部を中心に豪雪となる日本海側の気候、浜通り地方は温暖で雪の少ない太平洋側の気候、中通り地方はその中間的気候と、各地域で気候が異なっているのが特徴だ。
2022年の農業産出額は全国17位の1970億円。産出額の内訳は米約30%、畜産24・7%、野菜23・4%、果実15・2%となっており、米を中心に多種多様な作物が栽培されている。
主な農作物をみると、米(収穫量全国6位)、キュウリ(4位)、トマト(8位)、アスパラガス(9位)、モモ(2位)、日本梨(4位)、リンドウ(出荷量全国4位)。
県は福島県農林水産業振興計画で「『もうかる』『誇れる』共に創るふくしまの農林水産業と農山漁村」を基本目標として、多様な担い手の確保・育成、先端技術の導入やこれに対応する生産基盤の整備、GAPの認証取得促進、県オリジナル品種(「福、笑い」「ゆうやけベリー」など)の普及拡大によるブランド力強化、有機農業をはじめとする環境と共生する農業の推進に力を入れている。
2011年3月11日に発生した東日本大震災と原子力災害により、農林水産業はかつてない甚大な被害を受けた。大津波により生産基盤は大きく損なわれるとともに、原子力災害においては、国の避難指示や農林水産物の出荷制限、風評による販路の縮小と市場価格の下落など深刻な事態に直面した。
これまで農林漁業者、行政、団体等関係者の取り組みにより、原子力被災12市町村における営農再開率は約45%(2023年度末時点)にまで回復するなど福島県の農林水産業の復興・再生は着実に前進している。
特に浜通り地域等の失われた産業を回復するために、新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」が進められている。
農林水産業も重点分野の1つにあげられており、さらなる営農再開を図るために農地の集積や大区画化を進めるとともに、ロボット技術やICTなどを活用した先端技術の開発・実証や社会実装に取り組んでいる。
福島県農業は担い手の減少・高齢化が進んでいることから、少ない担い手での効率的な経営の展開が急務となっている。2021年3月に策定した福島県スマート農業等推進方針に掲げる「情報の収集と提供」「技術の実証・普及」「人材の育成」「新技術等の研究・開発」「農業基盤・情報通信環境の整備」の5つの柱に基づき、省力化、効率化に資するスマート農業技術導入のより一層の加速化に向け、技術の実証から普及、情報発信、人材育成に至る総合的な取り組みを実施している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
各社の対応:米価高で意欲高まる/福島県特集 |
|
| |
|
|
| |
昨年6月に就任した三菱農機販売(株)東北支社宮城支店宮城福島担当の成田浩之氏によると、米価高騰の影響により、全体の実績は前年度比で概ね好調に推移しているという。
主要3機種は新型田植機が好調だ。昨年2月にリリースした6条/8条の新型乗用田植機「XPS6」「XPS8」は、高速植え付けに対応した「トランスフォーム植え付けシステム」を新たに開発し、業界最速(1・95メートル/秒)の植え付けスピードを実現。農地の集約化が進む県内農家にマッチしている。
トラクタは小規模圃場で活躍するXSシリーズ(18・2〜25PS)が人気だ。ビニールハウス内などあらゆるシーンで活躍でき、小回りが効いて作業性が高い点が評価されている。秋の収穫作業が終わった後の1〜3月の受注も増えており、「見通しは明るい。このまま米価が安定してくれれば」と成田氏。
展示会は、大玉村で昨年8月に開催された第22回中古農機フェア(福島県農業機械商業協同組合主催)に参加した。物価高騰の影響で、リーズナブルで購入しやすい中古農機は人気が高い。後継者不足で新品を買うのが難しい人にも提案しやすい。実際に機械を見てもらうことで、「これならば新品を買おう」と考える人もいるといい、展示会は多様な顧客と出会える貴重な機会だ。
修理、メンテナンス事業も堅調。最近の機械は性能が上がっており、トラブルが少ない傾向にあるが、長く大切に扱う人が増えており、計画的にメンテナンスを依頼する人が多い。
スマート農業については、「福島県は他県と比べると普及が遅れがちだが、4月からRTK基地局が県内一円で運用開始されることで、飛躍的に導入が進むのではないか」とみる。
三菱ではスイッチ1つで直進自動操舵ができるSE―Naviの他、乗用田植機「XPS6」「XPS8」などを中心にPRを進め、より一層スマート農業を推進していく方針だ。
各社が様々な新製品を次々にリリースしている。「時代はスマート農業だが、ただ単純に各機種の特徴をアピールして購入を促すだけでなく、他の作業機の提案もしながら、スマート農機の販売をしていきたい」と成田氏。
スマート農機はコストや操作性など導入へのハードルが高いと思っている農家も少なくない。大規模農家だけでなく、小・中規模農家などそれぞれの農家に合わせた柔軟な提案をして、スマート農機の普及を進めていく。
主力商品の国産初のショートディスクハロー「KUSANAGI(クサナギ)」も年々販売台数を伸ばしている。ホームページで実演を受け付けており、問い合わせが相次いでいる。特に若い年齢層の関心が高く、納得して買ってもらえるように今後も実演を続けていく。
浪江町に本社を構える常磐菱農(株)(高野一英社長)は、昨年の実績はまずまず。トラクタとコンバインは伸び悩んでいるものの、新型のナビ付き田植機などは好調だという。スマート農機はナビ付き田植機やドローンに動きがある。
ただ、ドローンは初期コストをかけて終わりではなく、毎年のメンテナンスのためのランニングコストがかかるという課題があり、「そこをクリアしないと普及はなかなか難しいのでは」と慎重だ。
展示会は昨年2回、浪江本社と相馬営業所で開催した。震災の影響で浪江町を離れた人は多い。展示会を開催しても人が来るか不安を感じていたが、2023年に12年ぶりに開催。すると思いのほか多くの人が訪れた。懐かしい仲間と再会し、毎年開催してほしいという声も聞かれた。震災前は120人ほどだった来場者数が、今は150人ほどとなり、売上げも上々だ。
草刈機に注目が集まっている。展示会では手押しの草刈機BULL MOWER(ブルモアー)が売れ筋だ。背の高い雑草も綺麗に粉砕するのが特徴で、年間20台ほど動いているという。「今年はラジコン草刈機スパイダーモアーも実演を交えながら紹介し、アピールしていきたい」と意気込む。今年も3月と7月に展示会を開催する予定。
メンテナンス、修理の依頼はメーカーに関係なく様々な機種が整備工場に入ってくる。震災直後は修理依頼が殺到したが、その時に比べると依頼数はだいぶ落ち着いてきた。
浪江町出身の高野社長は東日本大震災の約10日前に3代目に就任した。2011年3月11日、本社の2階で展示会の準備をしていたときに震度6強の揺れが浪江町を襲った。ガラスがバリバリと大きな音を立てて割れ、ロッカーが倒れたり、書類が散乱したりした。幸いにも従業員の中に怪我人はいなかったが、「もう終わったと思った」と当時を振り返る。
浪江町から離れる人や閉業を決断した会社もあり、浪江町で農機を取り扱う会社は常磐菱農だけとなった。
震災直後は避難の関係で浪江町から100キロ離れた猪苗代町から浪江まで通ってくれた整備士もいた。
現在は浪江町、相馬市、いわき市平、田村市都路の4カ所に営業所を構える。震災前は営業所が7カ所あったが、南相馬市原町を浪江本社に統合し、浪江町津島と富岡町の2カ所は閉鎖した。「営業所が浪江だけなら廃業も考えたが、営業所が複数あったから、なんとか続けなければと気持ちを奮い立たせた」。
2022年7月には浪江本社をリフォームし、従業員がより働きやすい環境を整えた。高野社長は「地域に根付く販売店としてこれからも農家に寄り添い、会社を守り続けていきたい」と力強く語る。
浪江町には、県外から移住してトルコギキョウやストックといった花き栽培を始める人も増えているという。安定した収益の確保や移住者の定着にはまだまだ課題はあるが、震災から約14年が経ち、再注目されつつあるようだ。
ヤンマーアグリジャパン(株)東北支社南東北営業部中浜ブロックエリアマネージャーの吉田昌孝氏によると、昨年9月までは平年並みの実績だったが、米価が高騰した10月以降、コンバインや乾燥機といった秋商品を中心に順調に推移している。3月の決算では計画通りの見通しだという。コロナ禍で買い控えをしていた農家の購買意欲も高まっており、田植機やトラクタなどの春商品の売れ行きも後押ししている。
11月以降は各エリアで実演会を開いた。吉田氏は「購買意欲が高まっているこの時期に訪問を強化し、お客様に納得して買ってもらえるような提案を進めていきたい」と強調した。
今年4月から県内11カ所でRTK基地局が本格運用されることに伴い、人手不足解消の観点からもスマート農機がますます注目されていく。主にドローンや自動操舵に動きがある。特に被災地の浜通りは、営農再開に向けて農地の集積や大区画化を進めており、スマート農機は欠かせない存在になっている。
「ヤンマーのトラクタは直進アシスト仕様の比率が高くなってきている。RTK基地局が運用開始されることで、より具体的にスマート農機の提案ができるようになってきた」と吉田氏。
ラジコン草刈機も人手不足解消やコスト削減、農作業事故防止の観点から需要が増えている。2023年7月にリリースしたYW500RCは最大45度までの急斜面での作業を可能にし、草刈りの負担を大幅に軽減。遠隔操作により不安なく作業でき、作業がしづらい場所でも、送信機画面で機体の傾斜角度を確認できる。
今年3月から販売開始するYW500RC'AEはリコイルロープを引かずにセルスイッチ操作でエンジンを始動できるようになった。「YW500RCは発売以来、安定して売れている。今後も性能をアピールしていく」と吉田氏。
メンテナンスや修理の依頼も増加傾向にある。できるだけ機械を長く使いたい人や、農機のトラブルを少なくするために計画的にメンテナンスする人が多くなっているという。
続いて、大寒波で記録的な大雪となっている会津地方について。会津ブロックエリアマネージャーの島影守宏氏によると、積雪は例年の3倍以上で、雪が少なかった昨年に比べて除雪機の受注が急増している。
ビニールハウスが積雪で倒壊するトラブルが相次いでおり、従業員が総出で対応に当たっている状況だ。従業員はなんとか出社できているものの、道路の渋滞や通行止めなどの影響で通勤時間に通常の3〜4倍かかっているという。つい先日も会津若松市内にある事業所の目の前でトラックがスタックし、従業員が手助けした。
主要3機種の動きはコンバインを中心にそれぞれ好調だ。島影氏は「会津コシヒカリの生産がさかんな地域。米価高騰に加えて、今年は夏場の天候が良かった。これにより稲穂の丈が伸びて倒伏が激しくなり、刈り取りがスムーズに進まないケースが増えたことなどが要因ではないか」と分析する。これを受け、会津管内6拠点(うち3拠点は大雪の影響で来月に延期)で倒伏を避けるための稲づくり講習会を今月開催した。計100人以上が集まり、好評を得た。今後も農家の役に立つ講習会を増やしていく。
福島県内では営農面積10ヘクタール以上の担い手層の割合が高くなっており、10年前の2015年と比べて130%ほど増えているという。米価高騰は特に担い手層に大きく影響しており、面積の大きい農家の所得が確実に上がっている。「今後も担い手層は重要な取引先になってくる。様々な提案活動を強化することで福島県の農業を元気づけたい」と島影氏は語った。
(株)ISEKI Japan東北カンパニー福島営業部長の佐々木伸治氏は「昨年は極端な1年だった」と振り返る。天候不順などはなかったものの、上半期はヰセキの主製品の発売がなかったため、苦戦を強いられた。10月以降は米価高騰の影響で各機種にようやく動きが見られた。
主要3機種はトラクタ、田植機は横ばいだが、コンバインは好調だという。特にフロンティアファイターHFR4050の動きがいい。JAの共同購入コンバインなどの対抗馬であり、相乗効果で順調に推移している。
2023年末に発表したフロンティアマスターFMシリーズは反響が多く、実演後すぐに成約に結びついている。長時間作業でも疲れにくい乗り心地の良さや操作のしやすさなどが評価されているようだ。
また、草刈機の関連商品が好調で計画比、前年比どちらもクリアしている。トラクタの後ろに装着するタイプやスパイダーモアーなどが主流になっている。
夏の猛暑で雑草の生育が早くなっており、防虫対策の観点からも注目されている。草刈りは農作業の中で最も労力がかかるため、草刈機は省力化やコスト削減に役立ち、関連商品は値上げ前の駆け込み需要も見られた。
BFトラクタはゼロ金利キャンペーンの影響もあり、売れ行きは好調という。ドイツ製のサスペンションシートを採用した居住性の高さなどが福島県内の農家にも受け入れられている。
佐々木氏は「FMやBFを目的にしているお客様が多い。展示会や実演会でアピールするのみならず、常に営業所に置き、お客様の目につくように工夫している」と話した。
スマート農機は高精度農機用自動操舵システムCHCナビをメーンに据える。4月から県内一円でRTK基地局が運用開始されることもあり、問い合わせが増えているという。今後もCHCナビを重点機種として普及を進め、大規模ユーザーや法人向けの研修も定期的に開催する。
今年注力したいこととして佐々木氏は「アフターサービスの充実」を挙げた。常にアンテナを張り巡らし、情報をキャッチすることで、機械のメンテナンスやアフターフォローを強化していく。
実は最近の機械は故障が少ないという。各機種の性能が向上しており、ユーザーも扱いに慣れている。主要機を複数台持っている人も珍しくない。だからこそ計画的な点検が欠かせない。「メンテナンスをすることでお客様づくりにつなげたい。信頼関係を構築し、継続していくことが大切。地道に訪問活動を続けたい」と狙いを語る。
(株)南東北クボタの実績は計画比、前年比をともにクリアした。第二エリア長の大木勝治氏によると、年始は停滞していたものの、春の需要期から次第に盛り上がりを見せ、10月の米価高騰が後押しした。
主要3機種はトラクタと田植機は例年並みだが、コンバインが好調で、JAの共同購入コンバインの対抗馬として昨年4月に発売した、がんばろう!日本農業応援機・自脱型コンバインER448N Limited(48PS、4条刈)の販売台数を増やしている。
秋商品は乾燥機に動きがあり、今年の受注も増えてきている。各メーカーが4月以降に値上げを予定しており、昨年12月中の駆け込み需要も見られた。
スマート農機は精度の高い直進キープを中心に、自動操舵、ドローンの提案を積極的に行っていく。特にドローンの関心が高く、クボタ主催のドローン講習会への参加者も増えている。
展示会は昨年3月に郡山市の郡山カルチャーパークで「クボタスマートグリーンフェア福島2024」を開催した。ICT農機の展示や営農支援システムKSASなどを紹介。最新機種の試乗体験コーナーも人気だった。「来場者に若い世代が多くなってきており、非常に心強い」と大木氏は語る。
7月には山形県山形市の山形ビッグウイングで「クボタBIGサマーフェア2024」を開いた。モア祭りと題して、各メーカーの草刈り関連機械が一堂に集結。夏場の高温で日中に作業できない分、キャビン付きのトラクタに乗りながら草刈りをする人が増えているという。
今年は3月と6月に展示会を予定しており、RTK関連やドローン、自動操舵などのスマート農機を全面にアピールしていく。
コロナ禍で展示会のスタイルも変わってきた。コロナ流行前は昼食を提供していたこともあり、昼時に来場者が集中していたが、ここ数年は昼食の提供をなくしたことで分散型になった。目的を明確にする人が増え、短時間での滞在で回転率が良くなっている。
メンテナンス、修理は秋の刈り取り後のコンバイン点検整備キャンペーンを実施した影響もあり、受注は例年よりも多い。県北では、果樹栽培が盛んなので、スピードスプレヤーの点検依頼も増えている。県内数カ所のサービスセンターの他、各拠点ごとにも整備工場があり、様々な要望に応えられる体制を整えている。
今年は農作業安全の啓発に力を入れていく。事故防止のために、訪問の際に安全喚起を促している。今後は講習会の開催なども検討。
これからも社員一人ひとりがビジネスの原点に返り、マーケットインの考え方でお客様に寄り添うクボタの「On Your Side」の精神を大事にしていく。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
県の取り組み:RTK基地局を4月から運用/福島県特集 |
|
| |
|
|
| |
福島県内のスマート農業の導入経営体数は飛躍的に増えている。県は2030年度までに950経営体にする目標を掲げていたが、2023年度末時点ですでに990経営体に達したという。昨年9月に上方修正をし、2030年度までに1700経営体を目指す。機種別には主に自動操舵システム、ドローンを中心に導入が進んでいる。
今年の福島県内での大きな動きといえば、なんといっても4月1日から県内一円でRTK基地局が本格運用開始されることだ。RTK(Real Time Kinematic・リアルタイムキネマティック)とは、地上に設置した基地局からの補正情報を受信して測位精度を向上させるシステムのこと。これにより、農業機械の自動操舵システムやドローンの誤差数センチの高精度作業が可能となる。
県内11カ所にRTK基地局を設置し、年間利用料を徴収しながら運用していく方針だ。設置場所は相馬市、富岡町、いわき市、伊達市、三春町、矢吹町、棚倉町、猪苗代町、会津坂下町、南会津町田島、南会津町南郷の11カ所。これまでは南相馬市が独自に1カ所、GNSS固定基地局を設置していたのみだった。
また、県は昨年11月から12月にかけて、RTKシステムの理解促進、活用推進を図るための「RTK活用!スマート農業推進セミナー」を県内7カ所で開催。(株)南東北クボタの協力のもと、RTKを利用した自動操舵付きトラクタ、無人ロボット農機、ドローンなどによる圃場での実演も披露した。セミナーには延べ300人が参加し、スマート農業への関心の高さがうかがえた。
普及のために、GPS活用によるスマート農業加速化推進事業として、高精度測位システムを活用する自動操舵などのスマート農機の導入にかかる補助を行った。補助率3分の2以内で上限150万円と設定。補助件数は一次募集で65件、追加募集32件の応募があり、計97件となった。
今後も生産者向けのセミナー・イベントの開催や、農業短期大学校におけるドローンの実践的な知識や操縦技術を習得するための研修などを行う予定だ。
平地に比べて条件不利な中山間地域は導入が遅れているため、スマート農業を活用した地域農業モデルの構築・実証をするための事業も新たに立ち上げた。
福島県農林水産部農業振興課主幹(普及・農業革新担当)の丹治喜仁氏は「RTK基地局の運用開始で、スマート農業の普及をさらに加速させていく。そのための補助や体制を整え、儲かる農業の実現に向けて尽力していきたい」と意気込む。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
JA全農福島の動き:7月にアグリフェア開催/福島県特集 |
|
| |
|
|
| |
JA全農福島施設資材部農業機械課(菅野隆次長)は2024年度のこれまでの実績は、計画比106%、前年比107%と推移している。
主要3機種ではコンバインが好調。第3弾共同購入コンバインYH448AEJU(51・5PS、4条刈)は3年間で60台の供給を目標にしており、初年度の今年は目標15台に対し、すでに18台の受注がある。
「コンバインは5〜6条刈がメーンになっている。2〜3条刈に関しては中古に移行しつつある」と菅野次長。
田植機は横ばい。トラクタは昨年度までの共同購入トラクタSL33Lの受注が終了した影響で苦戦しているという。今後は共同購買で機種を絞った推進をすることで落ち込みをカバーしていく方針だ。
昨年7月に郡山市のビッグパレットふくしまで「アグリフェア2024inふくしま」を開いた。県下統一の農業機械展示会は新型コロナの影響で2019年以降は開催を見送っており、5年ぶりの開催となった。47社が出展し、会場では共同購入コンバインや、ネギ・ブロッコリー機械化一貫体系などをアピールした。
動員計画人数は目標2500人に対し、2698人(計画比108%)、成約目標3億8500万円に対し、約5億2000万円(計画比135%)となり、盛況だった。
今年も7月に開催を予定している。次はコメに着目し、「ライスセンターの提案、乾燥機などの機械化一貫体系を中心にPRしていきたい」と意気込む。
スマート農機は、各メーカーが多種多様な新製品を次々に発売している。課題はJA農機担当者を対象としたスマート農機に対応できる人材育成の強化。整備担当者向けの農業機械整備技能検定の資格取得へ向けた講習会の促進や、JAグループ農業機械検定資格取得の促進、各メーカーの新技術に対応した修理整備研修などを継続することで対応していく。
6条以降の田植機は直進アシスト付きがメーンになってきている。菅野次長は「RTK基地局の運用開始でスマート農機の普及が加速するだろう。担い手担当者と連携しながら実演試乗会を開催し、各機種・サービスの導入支援も進めていく」と話した。
被災地における農業復興については、浜通りの帰還困難地域の解除に伴い、営農を再開するケースが見られる。修理やメンテナンスの対応も必要になってきており、JAの農機センターなども活用しながら体制強化を図る。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
福島県農機商組の動き:注目の中古農機フェア/福島県特集 |
|
| |
|
|
| |
福島県農業機械商業協同組合(橋本盛光理事長、70組合員)は、昨年8月に大玉村のプラント―5大玉店で第22回中古農機フェアを開いた。成約目標8000万円に対し、約1億800万円、成約台数236台の実績を上げ、成約率64%と変わらず旺盛な中古需要をうかがわせた。
46会員と資材メーカー10社が参加。会場には41台のトラクタ、38台の管理機など計367台が並び、時には会場の中を歩けないほど多くの来場者で大盛況だった。
中古農機フェアは年々注目を集めており、できるだけ機械を低コストで活用したいというニーズが増えている。今年は7月17、18日に同じ会場で開催する予定だ。
副理事長兼事務局長の齋藤満氏によると、昨年の全体の実績は横ばいで推移している。主要3機種は若干台数が減っているが、「各社の値上げなどが影響しているのではないか」とみる。
確定申告対策として機械の先買いをしている人もみられる。米価高騰は生産者にとってはプラスになっているが、4月以降にさらなる値上げを予定しているメーカーもあり、この勢いにブレーキがかかるのではないかという懸念も。農業従事者が高齢化しており、資材費なども値上がりしている。厳しい状況には変わりない。先々の不安は尽きない状況だ。
昨年11月には福島市内で第2回農業資材展を開いた。昨年までは組合員のみで実施していたが、今年から一般客も受け入れた。反響は良かったものの、齋藤氏は「認知がまだ広がっていない印象を受けた。今年はいろんな地域から来てもらえるように、各方面からのアクセスが良い会場を設定して、集客を図りたい」と話す。
現在、農機整備技能士会を設立するためにJA全農福島と話し合いをしているところだ。2025年度中の設立を目指して準備を進めている。
農作業安全の啓発としてポスターやチラシの配布を行っているが、「安全啓発は地道なことを持続して訴えていくことが重要。事故は悲惨であり、これからもしっかりと取り組んでいきたい」と、頭を悩ませながら農作業事故を減らすためのより良い方法を模索している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
実証進む「新しい林業」/高性能林業機械特集 |
|
| |
|
|
| |
林業機械化が新たなフェーズに突入、確実に階段を上がっている。開発では、令和6年度の林業イノベーション現場実装シンポジウムで取り上げた「林業機械の開発・実証の現状」の報告内容が示すように、自動化、遠隔操作化への流れが大きく進展し、実用化、普及へと一歩を踏み出している。また、現場の対応も素材生産用ばかりでなく、急峻な地形の多い日本の林地にあって欠かせない架線系を含め、必要不可欠なものとして中身の充実が図られている。林業の機械化は、これからのリード役を果たし、牽引する立場がより鮮明になっており、林業現場の期待は引き続き高い。今週は、機械化林業を革新する取り組みともいえる「新しい林業」モデルの現状とともに、林業機械メーカーが取り組む現在の開発状況などを取り上げ、高性能な林業機械の今に焦点を当てた。
一般社団法人林業機械化協会(島田泰助会長)が事業実施主体となって進めている「『新しい林業』経営モデル事業」。同協会では2月5日に行った令和6年度の林業イノベーション現場実装シンポジウムの第3部で同協会が12事例の成果と課題について、次の通りまとめ、発表した。
▽北欧をモデルにした北海道・十勝機械化林業経営=北欧をモデルにした作業計画から素材生産、流通、再造林、保育に至る、新技術を導入した安全で収益性の高い作業システムを、北海道・十勝地方のフィールドを活用して構築。伐採計画から造林・保育までの収支改善と労働安全性の確保を目指している。
▽ICTを活用したCTLシステムによる垂直統合型モデルの構築・岩手=素材生産では、資源情報や地形情報から生産計画を作成し、現場作業を設計。ICTハーベスタの機能を活用し、現場の定量情報・地理的情報を共有。林業機械間の情報共有、フォワーダの集材作業支援により、CTLシステムの有効性の向上を図る。
▽川下側の需要を反映した効率的な素材生産 特定母樹「遠田2号」低密度植栽による低コスト造林 収支採算性向上の取組み・宮城=素材生産では、川下側の需給情報をICTハーベスタに指示して採材。検知は人力検知、写真検知、ICTハーベスタによる検知の3つの方法を実施・比較した。
▽新たな技術を融合する古殿町モデルの実証・福島=レーザ航測データを活用した路網設計支援ソフトや、クローラ型電動一輪車等の新技術を実証、「持続性確認可能木材」の表示につながる伐採位置情報の活用。素材生産では、一貫作業における林地残材の問題解消のため、マルチャーを活用して林地残材をチップ化。
▽川上と川下のデータ連携を柱とするコスト削減と山元還元の実証事業・長野=素材生産では、ICTハーベスタに造材指示をアップロード。乱尺造材、大型パネル製造に必要な丸太を集積。
▽最新式集材機とICTハーベスタ等を核とした主伐・再造林システム実証・普及事業・岐阜=岐阜県に導入例のない最新式林業機械を導入し、「新しい林業」の実現に向けて素材生産から販売、再造林・保育まで実証試験並びに普及活動を実施。素材生産では、油圧集材機・架線グラップルシステムによる集材作業及び研修会等による普及活動の実施。
▽需要地と供給地の事業連携・新しい地方創型SDGs林業への挑戦・三重・奈良=素材生産では、最適な架線計画作成と自走式搬器による架線集材、林内通信装置の導入。
▽先進的林業経営体によるタワーヤーダフル活用モデルの構築・和歌山=実証では、作業計画としてオープンソースのソフトウェア「QGIS」と「Excel」を活用した架線計画を作成し、伐採・搬出では、「新しい技術」を活用した林地残材の収益化のため、末木・枝条の粉砕・運搬、「QGIS」等を用いた到達経路等のシミュレーションの実証を進めた。
▽森林管理組織「リフォレながと」を核とした長門型林業経営モデル構築事業・山口)=スマートグラスやUAVレーザ、地上レーザによる精度の高い森林資源把握ICT機器を活用した境界の画定で施業地確保を行うとともに、素材生産では、ICTハーベスタや木材検知システムを導入、最適採材、生産管理等による収益性の向上、異業種からの参入を図る。
▽奥地化に適応した主伐・再造林作業システムの実証〜最新鋭の架線集材システムの導入〜・宮崎)=素材生産では、油圧集材機と遠隔操作グラップル搬器を組み合わせた架線集材システムを実証。
▽伐採・植栽・楽下刈一貫システム構築事業・伐採すぐコンテナ苗を植栽、防草シート、マルチャー下刈り・宮崎=素材生産では、箱形4トン・4WDダンプの活用、短尺材詰込用風呂敷型フレコンバッグによる丸太運搬車の輸送運賃及び地拵えの低コスト化。
▽持続可能な林業を実現する先進林業モデル―OSUMI(Oosumi SUstainable forest Management Initiative)モデル・鹿児島=素材生産では、チェンソーを利用しない生産システムの実証(ロングリーチグラップルソー、ハーベスタによる伐倒・木寄せ)、作業者位置を把握するアプリケーションでの作業。
「新しい林業」経営モデル実証事業は、令和6年度の実証地は、北海道、岩手、福島、長野、奈良、山口。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
林業イノベーション現場実装シンポで開発の現状、課題を共有/高性能林業機械特集 |
|
| |
|
|
| |
「〜新技術が拓く林業の未来〜」をテーマに、2月5、6の2日間にわたり開かれた令和6年度林業イノベーション現場実装シンポジウムでは、初日の第2部で林業機械の開発・実証の現状を取り上げて、実施。林野庁の林業機械開発関連の事業に取り組んでいる松本システムエンジニアリング(株)、イワフジ工業(株)、(株)諸岡、(株)NTTドコモの担当者が現状を報告し、国の林業機械開発ではメーンテーマとなっている自動化、遠隔操作化の進捗状況について説明した。4社の発表の後、東京農業大学非常勤講師である今冨裕樹氏による講評「機械開発・実証の現在位置と可能性」が行われた。
第2部では、松本システムエンジニアリングが手掛けている「ラジコン式伐倒作業車の遠隔操作技術・自動走行技術の開発・実証」については同社松本社長と技術部設計課の谷口利樹、中島晃也の両氏、「自動集材・造材マルチワークシステムの実証」の取り組みでは、イワフジ工業の舞草秀信、近藤乾太郎の両課長と実証試験に関わっている(株)中井林業代表取締役の中井稔氏らが登壇。
(株)諸岡が代表者としてパナソニックアドバンストテクノロジー(株)や(株)国際電気通信基礎技術研究所とともに進めている「フォワーダ集材作業の労働課題を解決する自律走行マルチオペレーション技術の開発」では、諸岡東日本営業部の中島泰生部長と国際電気通信基礎技術研究所の近藤良久氏が、また、(株)NTTドコモが(株)筑水キャニコムとともに取り組んでいる「自動運転型下刈機械の植栽フィールド運用実証」では、NTTドコモの担当課長である河田朋巳氏が説明に当たった。
松本システムエンジニアリングとイワフジ工業が進めている開発課題は、林野庁の令和5年度林業・木材産業国際競争力強化対策のうち林業のデジタル化・イノベーションの推進のうち「林業機械・木質系新素材の開発・実証事業」、また、諸岡とキャニコムが取り組んでいる開発課題は、令和6年度林業デジタル・イノベーション総合対策のうち「戦略的技術開発・実証事業」と事業こそ違うものの、いずれも自律走行、自動運転、遠隔操作など、現下の優先課題であるテーマに取り組んでいる。
開発課題は、林業の現場での負担軽減、省力化確保、安全作業の実現、施業の効率化を狙った取り組みで、実用化に向けて進んでいることを強く印象付ける報告、発表となった。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
イワフジの自動集材/高性能林業機械特集 |
|
| |
|
|
| |
イワフジ工業は「自動集材・造材マルチワークシステムの実証」(架線集材とプロセッサのワンオペ作業)について発表した。現在、架線式グラップルの「BLG―16R」と油圧集材機とを組み合わせ、完成を目指している新たな架線集材システムは、令和5年度にワンマンオペレーションを可能とする自動引き込みシステム、デジタルツイン映像表示などのAIマルチワークシステムとともに、同作業を実証。
「省力化」「労働災害の防止」の実現を図る取り組みとして6年度は、前年度に実証した自動引き込みシステムを、自動搬器送りからAIによる自動引き込み後、位置合わせ、荷掛け、横取り並びに搬送までを自動化したシステムに改良。そのため、搬器送りと横行を同時に行い、記憶した前回の荷掛け位置まで自動で直線的に移動する「自動引き込みシステム」をはじめ、自動荷掛けシステム(巻下げおよび地表面との距離検知を行いながら、AI画像認識で適正な位置合わせをして木を掴む)、自動横取りシステム(荷重検知をしながら適正荷重の範囲内で巻上げを行い、主索までを最短ルートで移動する)などを開発。林業現場での実証試験を(株)中井林業の協力を得ながら進めた。
現地での実証では、開発した各システムを操作し、自動荷掛け、自動横取り、AI画像認識そして造材から成る「自動集材・造材マルチワークシステム作業」の進捗状況を確認した。特に昨年度の課題として掴んだ「搬器空走行、索引き込みを自動化して自動制御時間に造材を行うが、時間が短いため、造材に要する時間が確保できない」に対し、同システムが対応・改善できるかの検証を進めた。
併せて従来型の「AIマルチワークシステム」等との比較検証から、現場導入に向けた分析も実施した。荷掛成功率、1サイクル当たり集材材積が改善できた場合、最大53・72立方メートルとなり、昨年度の1・4倍に生産性が上がることなどを確認、現場導入に当たっては今後の検証が必要となるとした。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
諸岡のフォワーダ集材/高性能林業機械特集 |
|
| |
|
|
| |
諸岡が代表者となって進めた「フォワーダ集材作業の労働課題を解決する自律走行マルチオペレーション技術の開発」。森林に適した無線通信であるSLAMを利用、フォワーダの自動走行として、有人走行後、ルート生成そして自動走行する技術の確立を目指した。
昨年度までの取り組みで実現した「実作業現場での安定した自動走行」や「安定かつ低遅延のWi―Fiの開発」、「障害物・路面形状の認識アルゴリズムの開発」を受けて今年度は、林内通信インフラとして林内全域通信網の実装・実現の開発から進めたのをはじめ、「予防安全」としてセンシング技術による予防安全機能の実装・実証、そして「複数台運行管理」として1台からマルチオペレーションシステムの確立を目指した。
諸岡フォワーダMST―1000VDLをベース車両に、自動運転最適化として(1)ICTシステムとの通信インターフェース追加(CAN)(2)センサの位置(GNSS・3DLiDAR・IMU・ホイールエンコーダ)などを改造。
共同開発のメンバーである東京農工大学は、林内通信インフラと自動運転精度の妥当性検証、(株)国際電気通信基礎技術研究所は、林内通信インフラ拡張無線LAN開発・試験・評価、パナソニックアドバンストテクノロジー(株)は、自動運転技術開発と予防安全機能の搭載及びマルチオペレーションシステムの開発・試験・評価、そして森林総研は、林内インフラ最適化計画の試験・評価をそれぞれ担当し、実装・実証を進めた。
林内通信インフラ向けの無線システムでは、広域無線通信を重点的に開発。システムを構成させた他、森林総研内試験場にフォワーダ2台の試験系を組み、基礎検証を実施。自動走行時の経路追従の情報から未来の車両の移動軌跡を予測し、走行可能エリアを逸脱する場合に警報及び、車両の減速・停止を行った。
また、管制システムを構築し、フォワーダ複数台での自動走行を行うマルチオペレーションシステムを想定したユースケースなどを実証した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
松本エンジニアリングの伐倒作業車/高性能林業機械特集 |
|
| |
|
|
| |
松本システムエンジニアリングが報告した「ラジコン式伐倒作業車の遠隔操作技術・自動走行技術の開発・実証」。昨年度の事業で、林業の安全な作業環境の構築、高生産・低コスト化そして従事者人口の増加を達成するために開発・実証を行った遠隔式伐倒作業車「シン・ラプトル」をより良くする改良を加えた。
生産性を高く、省力化できるような機械にするため、遠隔操作に関わる部分の見直しや自動走行技術の開発に取り組んだ。最大60メートルの距離で作業道から伐倒対象の立木に向かって走行し、伐倒した後、作業道に搬出するまでのサイクルタイムは、昨年の6分を下回る4分に改善。単純に効率にして約1・5倍に向上。また、1日8時間の作業で100本以上の立木を伐倒。間伐材1本0・3〜1立方メートルとし、1日約30〜100立方メートルとなり、平均で60立方メートル以上の生産量を実現している。
走行方式はクローラ式である開発機は、通常、標準シングルグローサシューを装備しているが、ゴムパッド付きトリプルシューや45度の傾斜専用トリプルシューの装着を可能としている。また、下り傾斜45度に対応できるよう設計されている。さらに、チェンソー方式での切断では、昨年の50センチに対し60センチに最大切断径を広げるなど作業性をアップさせている。
また、昨年のシン・ラプトルと比較し、(1)小型化、軽量化、特に薄型化した(2)上面の完全防水化(3)視認性の向上を図った。立体視映像システム「ティラノグラス」ARゴーグルを装着し、距離感を持って操作可能とした。実証試験の結果、スギの伐倒木で60センチの切断を可能とした他、下り傾斜50度付近での伐倒も成功した。
また、自動運転では、全長100メートルまで誤差が左右50センチ以内であることを確認したほか、山間部でも問題なく経路再現するなどの性能評価を進めた。開発機の諸元は、全長4130×全幅2400×全高2120ミリ、重量5500キロ、履帯中央部最低地上高610ミリ、履帯幅400ミリとなっている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
NTTドコモとキャニコムの自動運転下刈機械/高性能林業機械特集 |
|
| |
|
|
| |
令和6年度の「戦略的技術開発・実証事業」の実施課題として採択された「自動運転型下刈機械の植栽フィールド運用実証」は、(株)NTTドコモ、(株)筑水キャニコム、千葉県森林組合の3者が進めた。事業の概要は、(1)下刈り作業の自動化実証を行い、機械の自動化による施業効率を確認(2)下刈りの自動化を進める上で障害物等の位置情報の取得が必要となる。ドローン画像の映像解析や、穴掘りを実施する際に位置情報を取得する等の、地拵え後からの植栽までの作業のIoT化検証を実施(3)下刈機械及び運行監視システムの機能改善を実施―という内容。
キャニコムの新型車両「山なみ傾子」にGNSSアンテナや制御モジュール、カメラ搭載など自動運転機能を追加するなど改造。また、遠隔監視用タブレットを使って、自動運転及び遠隔操縦を可能とし、実証実験を行った。
その結果、画像解析では、「ドローン空撮の画像解析による伐根の検出は、伐採直後で地上色に同色化していないなどの条件が合えば可能」であることは分かったものの、「苗木の解析は難しい」との評価。
また、自動下刈り実証では、「走行の障害物となる残材・伐根を除くことで自動走行は可能。往復走行を行うことで施業全体の75%のエリアの下刈り処理を行うことができる」成果を引き出している。さらに、施業効率検証では、施業カバー率の高い往復走行パターンが、従来の刈払機と比べて4・9%の工数削減できる結果となったほか、下刈り作業としては施業時間を半分に短縮できることが分かった。
これらから、下刈りの自動化を目的とした施業地の整備ができる場所であれば、作業工数の削減を図ることができた、としている。現時点で自動運転による施業が可能な場所として、(1)縦傾斜の縦植えの施業地。起点側に奥行6メートルの旋回スペースが設けられること(2)走行の妨げとなる伐根は除去(3)苗木検知は難しいので、直線走行できるように植栽していただくなどを指摘し、条件を満たせばすぐにでも下刈りの省力化は可能とした。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
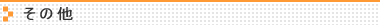 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
2025農機商戦が本格始動、先進技術をアピール |
|
| |
|
|
| |
春の農機展が各地で開かれ、2025商戦が活発に動き始めた。コロナ禍が明け、イベントは従来同様にもたれるようになったが、展示内容、推進重点項目には大きな変化がある。それは農業現場の現況もしくは今後を見越した技術対応であり、先進技術の提案になる。大規模営農で求められる省力化・省人化、作業のスピードアップ、適期作業にかなう栽培体系の採用と見合う機械化支援、そして作業の手を止めないための確かなアフターケアなど、これまでと同じ信頼の絆を元に、より高度な営業の腕をふるう年となる。昨年来の「いい流れ」を保ちつつ、実績の上積みを図りたい。
1、2月に各トラクタメーカーが開催した流通関係者との全国会議を経て、春の展示会シーズンを迎え、2025商戦が本格的にスタートした。昨年後半からの米価格上昇をバックに、農機に対する農家の投資意欲は久方ぶりに熱を帯び、乾燥機や調製機などの米に関わる秋商品はもとより、様々の機器が活発な動きをみせている。
今年の市場攻略に当たり、各グループが掲げた重点事項をみると、共通のテーマが盛り込まれており、1つは大型化する営農への対応。農業現場の人手不足を背景に、できるだけ省力的、効率的に作業を進めたいとの要求は間違いなく高まっており、機械の大型化あるいは作業精度を高いレベルに保ったままいかに作業速度をあげるか、こうしたニーズに応える機械技術の提供がキーポイントになる。加えて、技術的に未熟な従事者でも一定レベルの作業がこなせる体制を築くため、また、増加する管理圃場の効率管理を支えるためにも、スマート農機の採用にはさらにドライブがかかるとみられ、そうした先端技術の推進力が2つ目のテーマとなる。
すでに各地で実施されている農機展では、昨年来のいい流れを持続させるとともに、前述の農業技術の組み換え・再構築の取り組みをどのように牽引し支援していくかに重点が置かれていることが分かる。代表的なのは、トラクタの大型化・自動操舵の採用、プラス推進する作業機の変化だ。従来からのロータリ、ハローでも作業速度の向上に着目した開発が進んでおり、一方では、ディスクハロー、パワーハローといった牽引式作業機をアピールする場面が格段に増えた。有数の稲作地帯でも直播が見直され、適期作業や省人化の観点で直播と移植の組み合わせを検討する経営体が増加する中で機械化の体系も再考されている。
その他、稲作・畑作・野菜作の複合経営、自給率アップの一環となる耕畜連携の推進、施設化など、まさに農機商いの軸足は、変化対応に置かれている。商売の種は現場にある。先行きを見越した農機ビジネスを確立していきたい。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
輸出は1.5兆円突破/農林水産省・農産物の輸出拡大に向けて(上) |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は、農林水産物・食品の輸出額を2025年までに2兆円、2030年までに5兆円に拡大することを政策目標に掲げ、海外の規制・ニーズに対応した生産・流通体系への転換を図る「供給力向上の取り組み」と、現地系レストラン・スーパー等の新市場開拓を図る「需要拡大の取り組み」を車の両輪として推進している。今回は「供給力向上の取り組み」について、大規模輸出地モデル形成等支援事業を中心に動向をみる。
2月10日付既報の通り、農林水産省が4日に公表した「2024年の農林水産物・食品の輸出実績」によると、輸出額は1兆5073億円で、前年比533億円(3・7%)増と順調な動きをみせた。
この主な要因としては、日本食レストランの増加、インバウンドによる日本食人気の高まりなどを背景とした好調な外食需要のほか、事業者の販路拡大の取り組み等の進展―があげられた。
輸出額を国・地域別にみると、輸出先の第1位は米国2429億円(前年比17・8%増、金額構成比17・2%)、2位は香港2210億円(同6・6%減、15・7%)、3位は台湾1703億円(同11・2%増、12・1%)、4位は中国1681億円(同29・1%減、11・9%)、5位は韓国911億円(同19・8%増、6・5%)となっている。中国と香港においては、水産物の輸入規制の影響を受けて輸出額が減少したものの、それ以外の国・地域では大きく増額した。前年に比べ、特に輸出額の増加が大きかったのは、米国(367億円増、主な増加品目=ホタテ貝〈生鮮等〉、牛肉、日本酒)、台湾(171億円増、同=リンゴ、ホタテ貝〈生鮮等〉、牛肉)、ベトナム(165億円増、同=ホタテ貝〈生鮮等〉、植木等、牛肉)。
また、農産物のうち、前年からの増加率が高かった品目では、米(援助米除く)120億2900万円(前年比27・8%増)、緑茶363億8000万円(同24・6%増)、かんしょ36億200万円(24・3%増)、リンゴ201億3600万円(20・5%増)、ブドウ59億3200万円(14・7%増)、モモ29億5300万円(13・2%増)、柑橘14億8700万円(11・9%増)などがあげられる。
農林水産省は、さらなる輸出促進策の1つとしてグローバル産地づくり推進事業をあげ、令和7年度予算概算に5億9200万円を計上。国内の生産基盤や食料の安定供給体制の強化を図るため、海外の規制・ニーズに対応した生産・流通体系への転換を通じた大規模輸出産地の形成等を支援するほか、GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)を活用した伴走支援、輸出人材の育成・確保等を支援するとともに、品目等の課題に応じた取り組み支援を行う。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
EIMAが示す農の未来:「農業5.0」へ移行/イタリア・国際農機展レポート |
|
| |
|
|
| |
連載の最後に、EIMA2024で開催された様々なイベントをみる。既報の通り、EIMA2024では、11月6〜10の5日間の開催期間中に、数多くのイベントが行われた。トークショーやセミナー、記者会見、会議、ワークショップをはじめ、トラクター・オブ・ザ・イヤー2025や革新的農業生産の表彰式、出展企業のプレゼンテーション、最先端のロボット技術のデモンストレーション、最新トラクタの実演パレードなど、屋内外で様々なイベントが毎日実施されていた。主催者によると、合わせて行われたイベントは150にのぼったという。そのうち、会議の題目について一部をみると、農業機械産業の技術や市場、ヨーロッパ農業の課題、イタリアによるアフリカの開発支援「マテイ計画」、「水」と気候変動の問題、パルミジャーノ・レッジャーノのサプライチェーンについて、SNSから生まれた農業インフルエンサー、農業の意思決定支援システムの重要性―など非常に幅広い。会議やセミナーの一部はライブストリームにて、インターネット動画が生配信され、世界中に届けられていた。また、イベントは会場内だけでなく、見本市会場があるボローニャ市内でも実施された。ここでは、数日間の取材中に触れることができた、いくつかのイベントについて概要をみる。初日の朝には、会場1階ホールにて、開幕のテープカットセレモニーに続いて「農業機械産業の技術、専門スキル、市場:農業企業の新たな課題」の会議が行われた。同会議には、イタリア国のフランチェスコ・ロッロブリージダ農業・食料主権・森林大臣をはじめ、ヴァレンティノ・ヴァレンティーニ企業・メード・イン・イタリア省副大臣、EIMA主催者であるFederUnacomaのマリアテレサ・マスキオ会長、イタリア貿易促進機構(ICE)のマッテオ・ゾッパス会長、イタリア農業連盟(CIA)のクリスチアーノ・フィニ会長、同国最大の農業団体であるコンファグリコルトゥーラのルカ・ブロンデッリ副会長が出席。農業企業にとっての新たな課題や挑戦について意見交換を行った。議論では「高付加価値作物に特化したイタリア農業経済にとって技術への投資は収量を増やし、生産性を上げ、農作物の品質を向上させる重要な要素である」ことが示されたが、こうした投資について「農業所得や収益性の低さ」や「投入資材を削減しつつ土壌肥沃度を維持向上する複雑な課題への対処」などが壁になっていることがあげられた。この点について、生産コストの上昇は特に原材料や燃料の価格上昇によるものが大きいことから、ヴァレンテーニ副大臣が第二世代となる原子力発電の立ち上げに言及。さらに、ロッロブリージダ大臣はイタリアにおける2024年版「農業イノベーション基金」について発表した。同基金は、デジタル経営管理、機械、ロボットソリューション、センサー技術、節水や化学物質の使用削減、副産物の利用など、利用可能な最善の技術の普及を通じて、農業、漁業、養殖業の生産性向上を目指す投資を支援するもの。支援対象は主に同国内の農林水産業関連の中小企業で、基金の総額は1億ユーロ。対象技術はトラクタなどの農業機械や工具・設備をはじめ、農用運搬車、畜産・水産の関連機械などとされた。EIMAが同基金の発表の場に選ばれたという事実は、イタリア農政にとってもEIMAが大きな意味をもつことの証左なのだろう。これを受けて、主催者のFederUnacomaは、「不利な経済状況に直面しても、新しい技術や機械への投資を支援することは重要だ」とした。また、2日目に開催されたワークショップ「農業機械:常に進化し続ける農業のバックボーン」では、フィレンツェ大学のマルコ・ヴィエリ氏による講演「精密農業の現状:技術の現状と将来展望」及び、イタリア農業機械連盟であるCAI AGROMEC、同国で精密農業サービスを手掛けるDiagram Group社の代表者らなどによる「農業技術応用における農業機械企業の役割」についての意見交換が行われた。本連載を通して、数日間の取材から記者の目に映ったEIMAの姿を伝えてきた。連載の終わりに思うことは、これらはあくまでEIMAの一部に過ぎないということである。広大な会場内ではまだまだ多くの展示やイベント、プログラム、発表などが行われ、活発な情報交換が繰り広げられていた。EIMAは、農業関連見本市の中で最もグローバル化されたものの1つであり、各国の先端技術が集う展示会である。次回のEIMA2026は2026年11月10〜14日に、イタリア・ボローニャで開催される。ぜひ現地に行って、自身の目で世界の農機事情の最新動向を確かめてほしい。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
